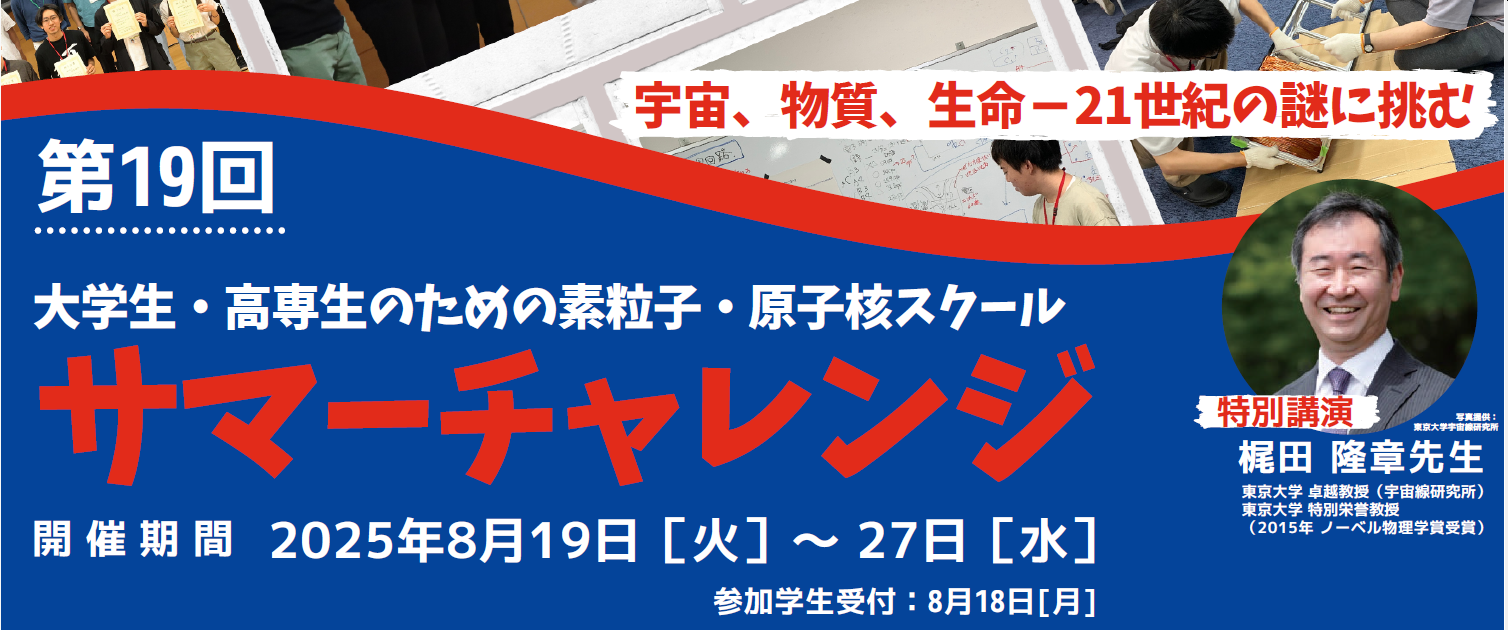過去にサマーチャレンジで学んだ卒業生から、
皆様への熱いメッセージです。
角谷爽 (18期生) 大阪公立大学理学部物理学科

自分が「サマーチャレンジ」に参加して、個人的に思ったことを挙げてみます。
参加する大きな意義として物理を知ること以外に、「人とつながる」ことだと思います。つながることでもしかすると今後の人生でここでの縁がきっかけで、面白いことが起きる気がするからです。
物理学科じゃなくても、もちろん物理学科であっても「サマーチャレンジ」に興味を持った方は参加したほうが良い気がします。私が参加したとき(去年)、物理学科だけではなく医学などの様々な分野の方が参加していました。
講義や演習内容についていけるか、あるいは人間関係などを心配するかもしれません。無責任な発言をしますが、多分なんとかなります。
前者については、サマーチャレンジに関わってそうな内容をある程度は予習すれば大丈夫です。(そこまで怯えなくても大丈夫だと思います。)後者については、他の参加者も同じ心境ですので話しかければすぐに受け入れてくれるはずです。私は、恐竜が絶滅しのは何年前か最近まで知らなかったほど偏った人物なのですし、他の参加者に話しかけて、拒絶されたこともなかったです。
演習はチームで行うので嫌でもコミュニケーションが必要になります。たとえシャイな人でも気がつけばしゃべることになるので、人とつながる機会はたくさんあります。初対面でも親切に指導してくださる院生や先生方のもとで、志を共にする全国の同級生達との学びの場である「サマーチャレンジ」。今まで「探求心とはいったいなんぞや・・・」と思っていましたが、「サマーチャレンジ」に参加して「探求心」を知ることができました。
笹森玲那 (17期) 新潟大学大学院 自然科学研究科 数理物質科学専攻 物理学コース

「全国から数十人の定員…。まさか自分が参加できるわけがない…。」そう思いながらこのページをご覧になっている方も、いらっしゃるのではないでしょうか。実は、私もまさにそう思っていた一人です。B3のとき、大学の先生からチラシをいただき、サマーチャレンジの存在を知りましたが、最初は「私には難しいかも…。」と半ば諦め気味に眺めていました。それでも、思い切って応募してみたところ、ありがたいことに参加の機会を得ることができました。
私が参加したのは、「放射線検出器を作ろう」というテーマの演習です。検出器の製作から測定までの一連の流れを体験しました。全国から選ばれた学生たちと一緒に活動する中で、自分の力不足を痛感する場面もありましたが、それ以上に学びや気づきが多く、非常に充実した時間でした。班には、プログラミングが得意な人、考察の整理が上手な人、スライドやポスターづくりが得意な人など多様なメンバーが集まっており、お互いの強みを活かして協力し合うことができたのも印象的でした。チームで物事を進めることの大切さを、身をもって実感しました。
そして現在、私が取り組んでいる研究テーマは「医療用放射線検出器の開発」です。サマーチャレンジでの経験が今の進路につながっており、参加できたことは”運命”だったのかもしれないと感じています。また、演習本番だけでなく、後に参加したOBOG会での出会いや交流も、自分の視野を広げる貴重な機会となりました。
サマーチャレンジには、物理に限らず、化学や工学などさまざまな分野の学生が集まっており、演習や交流を通して新たな視点や刺激を得ることができます。少しでも興味がある方、実習や発表を通じて成長したいと考えている方には、心からおすすめします。ぜひ、勇気を出して応募してみてください!
秋山雅志 (17期) 新潟大学大学院 自然科学研究科
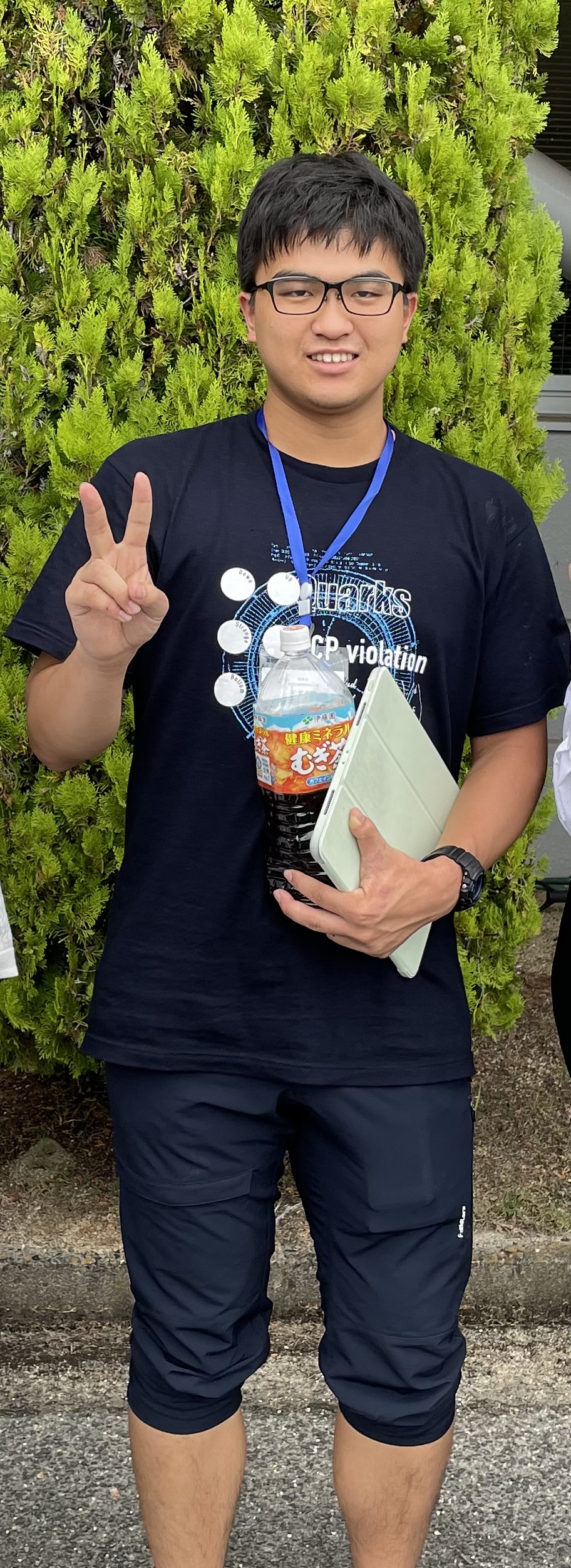
当時の私と同じ境遇の人の背中を押せたらと思い、メッセージを綴ります。
当時の私は、自ら「サマーチャレンジ」のようなイベントに参加するタイプではありませんでした。といのも、「他大学の人と関われる実力が自分に備わっているのか分からないし、実力が伴ってなかったら怖い」と感じていたからです。そんな中でも、周りに参加する友人がいたことがきっかけとなり、迷いながらもギリギリ応募しました。でも、今振り返ると間違いなく参加すべきだったと思います。印象深いのは「参加者の意識の高さ」と「ある程度の挫折感」で、地方大にいた私にはカルチャーショックでした。だからこそ、特に私のような地方大の方には、ぜひこのような経験をして欲しいと感じています。挫折感もありましたが、それでも「なんとかなる」ということを学びました。そして、自分の成長を実感できましたし、何より本当に楽しかったです。今では、いろいろなイベントへの参加や奨学金の申請などにも積極的に挑戦できるようになりました。当時の私と同じように、まだこのようなイベントに参加したことのない方は、この「サマーチャレンジ」をきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
数年前になりますが期間中の記憶も少し,,, 私は班長をしていたので、毎朝班員を起こすところから1日の始まりでした(笑)それほどに同じ演習班の人と関わる時間は非常に多く、仲がとても深まります。一方、夜にはほとんどの班がフリールーム的な部屋でデータ解析をしており、他の班の人たちとも「解析が進まないね~」なんて雑談しながら作業したことを覚えています。このように他の班の人と話す機会もたくさんありました。また、自信のない私でも、班長をしたり、実験装置を作ったり、意外とできることはたくさんありました。ちなみに、私は物性理論ですし、2年生や化学、工学の人も参加していたので、専門外でもあまり気にしなくて大丈夫だと思います。
中林拓帆 (16期) 総合研究大学院大学 素粒子原子核コース

僕は光子の粒子性を調べることを目的として演習を行いました。
演習では普段話すことのできないようないろいろな大学の人と話すことができました。
また、大学で行うような実験と違い、目的だけを与えられて、それを達成する過程や実験自体を自分で考えるので特に初めのうちはとても苦労しました。
具体的には、光子の粒子性をどのような実験で証明するかということで、MPPCを使った光の粒子性の計測に挑戦したのですが、MPPCの特性上、光が粒子であることの証明ができないという結論に至りまた振出しに戻る、というようにあっているかわからないまま進めていくところにとても苦労しました。しかし自分たちで考えて出した結果だったので最後の成果発表会では自信をもって発表することができたと思います。後から考えてみると実験に使う実験器具や周辺の知識が自然とつきとてもいい経験になりました。
講義では講義で習った内容が実習で出てきたり、講義で出てきた装置を実際に見学できたりと意識をしなくても自然と知識を身に着けられるように構成されていたので、楽しみながら必要な知識を得ることができました。