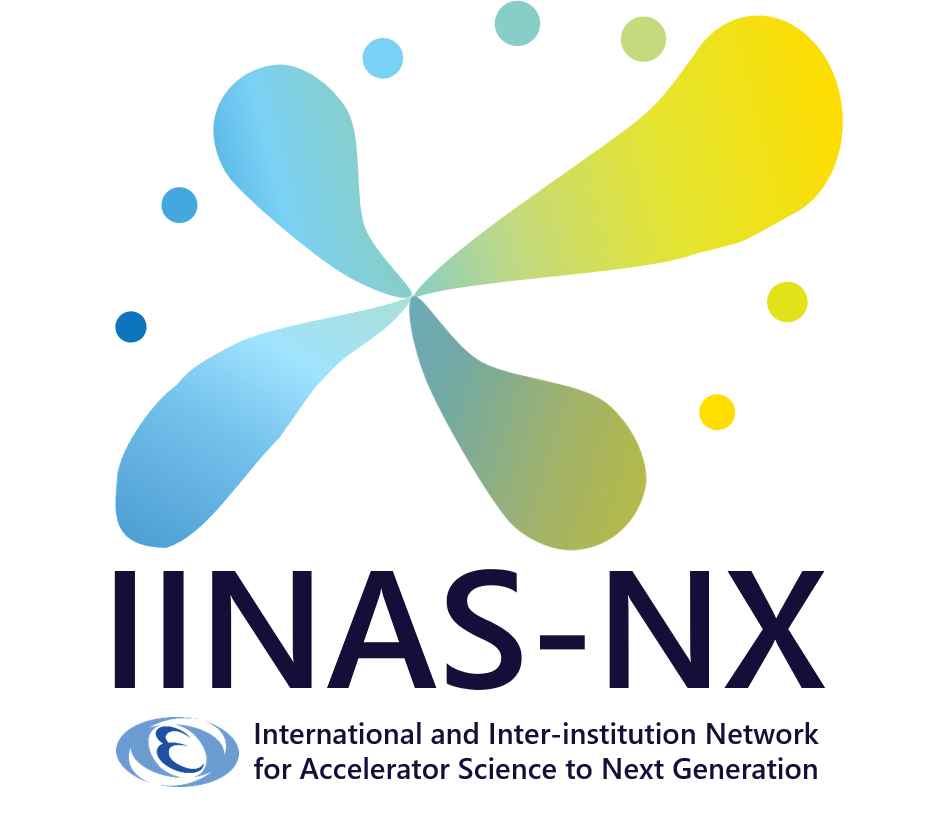2025年度
第14回ストレンジネス核物理国際スクール (SNP Schoool 2025)
- 開催場所: 大阪
- 開催期間:2025/12/1-2025/12/5
- Links: Home page, photos
- 報告: 今年度(SNP School 2025)は大阪大学吹田キャンパス・銀杏会館でオンラインも併用したハイブリッド形式を行った。6名の講師による核物理関連の講義、RCNP加速器施設見学、参加学生49名による口頭発表(Young Researcher’s Session, YRS)を行った。YRSでの発表者には修了書を授与し、また。組織委員・講師などの投票により優秀者8名を表彰した。参加者数は、講師・組織員も含め91名(うち対面参加者は65名)であった。
- 代表者:高橋俊行 (KEK・素核研)
第14回AONSA/第9回中性子・ミュオンスクール
- 開催場所: 東海
- 開催期間:2025/11/17-2025/11/21
- Links: Home page, photos
- 報告: 2025年11月17日から21日にかけて、茨城県東海村にて第14回AONSA中性子スクール/第9回中性子・ミュオンスクールが開催されました。今回のスクールの主催組織の一つであるAONSA (The Asia-Oceania Neutron Scattering Association)は、アジア・オセアニア地域における中性子科学会連合でありまして、地域における中性子研究のコミュニティー拡大のための活動の一環として、中性子サイエンスの初心者へ講義及び実習を提供するスクールを開校しております。今年度の中性子・ミュオンスクールは、このAONSA中性子スクールとの共催となりました。さらに、今年度のスクールは、IAEAの協賛のもと開催されました。中性子・ミュオンビームを使った物質科学研究を学ぶため、日本を含む11ヵ国から合計38名の参加者が集まり、この分野で国際的に活躍されている研究者の方々を講師に迎えて各種実験手法のレクチャーを受けました。期間中の後半では大強度陽子加速器施設J-PARC物質・生命科学実験施設において、実際に中性子・ミュオン装置に触れて実験方法や解析方法を学びました。本スクールでの経験を活かして、今後の当該分野を支える人材へ成長してくれることを期待しています。
- 代表者:大友季哉 (KEK・物構研)
高専における加速器人材育成のための講演会
- 開催場所: 新居浜工業高等専門学校
- 開催期間:2025-10-16
- Links: Home page
- 報告:
令和7年10月16日(木)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)加速器研究施設の准教授・宮原房史氏および放射線科学センター助教・坂木泰仁氏をお招きし、加速器人材育成を目的とした講演会「加速器科学で切り拓く先端量子技術」を開催した。本講演会は、電気情報工学科4年生を中心に全学科の学生を対象として実施し、オンラインにより全国の国立高専にも同時配信を行った。
講演では、宮原氏から加速器の基本的な仕組みや、その技術が応用されている最先端の研究について紹介があった。続いて、坂木氏からは放射線の性質や、物質中での挙動を予測するシミュレーション研究についての解説があった。また、両氏は、加速器科学や放射線科学を学んだ後に活躍できる分野やキャリアパスについても紹介され、学生にとって将来を考えるうえで非常に有意義な機会となった。 - 代表者:田窪洋介 (新居浜高専・電気情報工学科)
加速器・レーザー若手スクール
- 開催場所: 広島
- 開催期間:2025/09/14-2025/09/15
- Links: Home page, photos
- 報告:
本スクールには、加速器・レーザー分野の大学院生・若手研究者に加え、素粒子実験などの周辺分野や企業関係者も参加しました。参加者の所属学会は日本加速器学会、レーザー学会、物理学会、プラズマ・核融合学会と多岐にわたり、普段は交流の機会が少ない若手研究者同士の横のつながりを築く良い契機となりました。
講義は加速器・レーザーそれぞれ3つのトピックについて実施しました。講師の先生方には、理工系修士1年生を対象としたレベルを想定し、基礎から分かりやすくご説明いただきました。アンケートでも「初心者向けの内容で他分野の話も理解しやすく、参加したいと思えた」といった声が寄せられ、異分野の技術を初歩から学ぶ貴重な機会となったことが確認できました。
また、特別講演として東京科学大学の山崎詩郎先生に「オッペンハイマーの科学」と題し、科学を社会に伝える取り組みについてご講演いただきました。NHK Eテレをはじめ多数の番組で科学監修・出演をされている山崎先生から直接お話を伺うことは、科学コミュニケーションを学ぶ非常に貴重な機会となりました。アンケートでも「今後もこのような講演を実施してほしい」との回答が9割以上を占めていました。
以上より、本スクールはレーザー分野と加速器分野の大学院生や若手研究者を対象に、両分野に共通する基礎技術を体系的に学ぶ機会を提供するとともに、研究者間ネットワーク形成を加速する成果を挙げました。 - 代表者:大谷将士 (KEK・加速器)
第8回ビーム力学と加速器技術のための国際スクール
- 開催場所:中国 上海
- 開催期間:2025/09/01-2025/09/10
- Links: Home page
- 報告: 2025年9月1日から10日にわたり,ISBA25(第8回ビーム力学と加速器技術についての国際スクール)が広島大学とSARI(ShanghaiAdvancedResearchInstitute)の共催により、SARIを会場として実施された。10日間のスクールでは、加速器の基礎から応用、最新研究(AI応用や第4世代放射光源)までの講義に加え、ASTRA・ELEGANT・GENESISを用いたシミュレーション実習が行われた。学生はグループ発表を行い、優秀チームには賞が授与された。研究紹介の学生セッションやコミュニケーションセッション、遠足やバンケットを通じ、人間関係形成や国際交流も重視された。研究所ツアーではSSRF、SXFEL、建設中のSHINEを見学し、最新加速器技術を体感した。最終日には修了証と各種表彰が行われ、アンケート結果では講義・実習の質やレベル、人脈形成効果が高く評価され、全体として充実したスクールであったことが示された。
- 代表者:栗木雅夫 (広島大学先進理工系科学研究科)
第19回サマーチャレンジ
- 開催場所: KEK
- 開催期間:2025/08/19-2025/08/27
- Links: Home page, photos
- 報告: 33の機関(大学)から参加した72名の学生が9日間、講義や実習からなるプログラムに取り組んだ。素粒子、原子核、宇宙、統計、加速器、放射線の講義に加え、梶田隆章氏による、自身の経験を交えた「研究の楽しさ」についての特別講義に熱心に耳を傾けた。素粒子、原子核、加速器、放射線、物性に関する12の課題に、それぞれ6名のチームが挑戦し、演習担当教員と大学院生のTAから直接指導を受け、座学から実験のセットアップ、データ収集、解析までを試行錯誤しながら行なった。施設見学ツアーでは、各施設で実験を行う研究者の案内で、普段なかなか入ることのできない加速器トンネルや検出器を間近で見学した。最終日の成果発表会に向けて、各班で発表練習とプレゼンテーションのブラッシュアップを重ね、本番では物理学会さながらの雰囲気で活発な質疑や議論が行われた。
- 代表者:齊藤直人 (KEK 素粒子原子核研究所)
第八回粒子物理コンピューティングサマースクール
- 開催場所: KEK
- 開催期間:2025/07/28-2025/08/01
- Links: Home page, photos
- 報告: 粒子物理コンピューティングサマースクールは、素粒子、原子核、宇宙線・宇宙物理分野における計算機利用技術を習得するための、大学院生を対象としたスクールです。第八回となった今回は、2025年7月28日から8月1日の五日間、KEKつくばキャンパスを会場に開催し、全国11大学21研究室から27名の大学院生が参加しました。講習内容は、参加者全員が受講する共通講習として、計算機とネットワークの基礎と応用技術(GPGPU、コンテナ、クラスター、Grid)とデータ解析に必要な技術(統計解析、機械学習、シミュレーション)、さらに量子コンピューティング、リアルタイムコンピューティングを行いました。午後の講習では、計算機応用コース(Deep Learningの実践、Modern C++、ソフトウェア開発ツール)とATLASソフトウェア講習をパラレルで行いました。最終日に行った実習成果発表会では、参加者全員がそれぞれ5分の持ち時間で、4日間で取り組んだ課題について工夫を凝らした発表を行いました。
- 代表者:田中 純一 (東京大学・素粒子物理国際研究センター)
MAPSアカデミー
- 開催場所: KEK
- 開催期間:2025/07/23-2025/07/30
- Links: Home page, photos
- 報告:
2025年7月23日から30日の8日間、素粒子原子核研究所(素核研)主催で「MAPS アカデミー」がKEKつくばキャンパスで行われました。
MAPS(Monolithic Active Pixel Sensor:モノシリック型アクティブピクセルセンサー)はCMOS技術を用いた半導体検出器のことで、小型・高性能かつ低コスト化が可能な次世代センサーとして注目されています。さらに、将来の加速器実験でのトラッキングやカロリメータ、ミューオン検出器など幅広い応用も期待されています。
MAPSアカデミーは、MAPSの設計・開発に必要な基礎知識とスキルを学ぶことを目的とした、若手研究者向けの集中プログラムです。参加者はMAPSの動作原理から最先端の開発状況についての講義を受けつつ、MAPSの設計や運用の実習を行いました。素粒子・原子核物理やセンサー工学など幅広い分野から定員の3倍以上の応募があり、選抜された20名が参加しました。フランスとドイツからの6名を含めた10名の講師と合わせ、世界各地から集まった参加者らで国際色豊かなスクールとなりました。 - 代表者:江成祐二 (素粒子原子核研究所)
SOKENDAI KEK Tsukuba/J-PARC Summer Student Program 2025
- 開催場所: KEK, J-PARC
- 開催期間:2025/06-2025/09
- Links: Home page, photos
- 報告: 本スクールは、意欲の高い学生にKEKの実験などを実体験してもらうことで、KEKや総研大に興味を持ってもらい、総研大への進学や将来のKEKとの国際連携の中心となる研究者への育成を目指すことを目的としている。今回は、453名の学部・修士課程相当の学生から応募があり、19名を採択した。参加者は、「素粒子物理」「物質・生命科学」「加速器」などの中からプロジェクトを選び、KEKのつくば又は東海キャンパスに4-8週間滞在して、受入れ教員のもとで研究を行った。また、J-PARC、Belle II、Photon Factory などの研究施設の見学を行ったり、講義を受けたりした。本スクールで得た経験をもとに、総研大またはKEK/J-PARCのプロジェクトに参加している国内外の大学院への進学につながることが期待される。今回の応募者は非常に多く、このプログラムが諸外国にも認知されてきたといえる。
- 代表者:西田昌平 (KEK 素粒子原子核研究所)
CERN サマー・スチューデント・プログラム 2025
- 開催場所:スイス CERN
- 開催期間:2025/06-2025/09
- Links: Home page, photos
- 報告: CERN Summer Student Programmeは、毎年世界各国から300名以上の学生が参加し行われている。参加学生は2ヶ月程度CERNに滞在して特定の研究グループに所属し研究の補助をするほか、講義を受講し、最先端の素粒子原子核物理、加速器、計算機、放射線遮蔽技術等の最先端の分野を学ぶ。日本からの学生派遣は、KEK-CERN間の覚書に基づいて2004年から始まり、今回の4名を加えるとこれまでに91名を派遣している。プログラムに参加した多くの学生が有意義だったと報告しており、大学院を修了後、ポスドク等になって世界各地で活躍している。
- 代表者:戸本誠 (KEK・素粒子原子核研究所)
第13回高エネルギー物理春の学校2025
- 開催場所: 豊橋
- 開催期間:2025/05/22-2025/05/24
- Links: Home page, photos
- 報告: 素粒子物理実験の面白さを伝え、大学院の学生同士の繋がり広げる目的で、第13回高エネルギー物理春の学校を開催した。講師を含むスタッフ13名(この内3名が春の学校のOB)、23機関から79名の学生受講者が参加した。ほぼ修士1年生の参加であったが、修士2年生が4名参加した。女性比率は25%だった。講師による6個の初学者向けの講義と、学生による17個の口頭発表と50個のポスター発表、学生によるパネル討論があった。講義内容は、素粒子理論、検出器、BelleII、ATLAS実験など、基礎から実験のフロンティアまでカバーした。学生からの活発な質疑があり、講義のあとも講師との議論が続いた。学生の発表における質疑では、司会が捌ききれないほどの挙手があり、学生の積極的な参加が見られた。ポスター発表では、学生同士の活発な議論が深夜まで続き、交流が深まった。パネル討論では、あらかじめ学生から討論のテーマを募集し、学生が素粒子実験を志した動機、勉強やスライドの作り方、社会貢献、キャリアパスなどについて議論した。学生が講義により素粒子実験の基礎を学ぶことができ、また多くの仲間を得てくれた。実施後の学生のアンケート回答での評価も高く、今後もこのような機会を提供していきたい。
- 代表者:南條 創 (大阪大学・大学院理学研究科)
TYLスクール:理系女子キャンプ2025
- 開催場所: KEK
- 開催期間:2025/04/02-2025/04/03
- Links: Home page, photos
- 報告:
「TYLスクール:理系女子キャンプ」は、女子高校生を対象にKEKつくばキャンパスで、科学実験やパネルディスカッション、講義、施設見学ツアーなどへの参加を通じて、理系への進路について考えてもらおうという企画です。2025年度は、全国から応募した30名の参加者に対し、霧箱を使った科学実験、外国人を含む第一線で活躍する女性科学者による講義、加速器体験ツアー、女子大学院生との交流などのプログラムを実施しました。
参加者アンケートでは、同じ興味を持つ同年代の参加者との共同作業、女性研究者の経験談、加速器実験に携わるKEK研究者とのふれあい等によって、研究の楽しさと奥深さ、国際性の重要さについて学ぶことができた、これまであまり接点がなかった女子大学院生との交流を通じて、進路決定や理系の学部での勉強や大学院での研究活動に具体的なイメージを持つことができた、という感想が寄せられました。
このように「TYLスクール:理系女子キャンプ」は、女子高校生が科学への関心を深め、研究者としての将来像をポジティブに描く機会となっています。
KEKトピックス記事を参照してください。 - 代表者:飯田 直子 (高エネルギー加速器研究機構)
2024年度
第6回アジア加速器用超伝導・低温技術スクール
- 開催場所:中国 北京
- 開催期間:2025/03/23-2025/03/30
- Links: Home page
- 報告: 2025年3月23日から3月30日まで、中華人⺠共和国北京市懐柔区にある高能物理研究 所(IHEP)・懐柔キャンパスで第 6 回アジア加速器用超伝導・低温技術スクールが開催され た。受講者は 58 名、講師(実習を含む)は 32 名で、受講者と講師の国籍は、日本以外で は、中国、インド、タイ、韓国、イタリア(勤務先はスイス)の 6 か国であった。スクー ルの内容は、各国の超伝導加速器や超伝導空洞、超伝導磁石、低温工学に関する 22 の講義 と、高周波空洞、高温超伝導体、低温工学関係の 6 種類の実習を行った。また、スクール 1 日目と 2 日目には IHEP の High Energy Photon Source (HEPS)と Platform of Advanced Photon Source technology R&D (PAPS)の見学を行った。受講者は実習のために 6 グループ に別れて行動したため、特に各グループ内でアジア地域の国々から若手の研究者・技術者 や学生・大学院生が交流を深め、国際的な人的ネットワークが形成されていた。
- 代表者:仲井 浩孝 (KEK)
パルス中性子源で使用する放射線検出器
- 開催場所: 札幌
- 開催期間:2025-02-28
- 報告: 北海道大学(北大)と高エネルギー加速器研究機構(KEK)は、北大所有の小型加速器中性子源を用いて10年以上にわたり共同で加速器中性子を利用したエネルギー分析を含めた中性子検出器に関する講義・実習を進めてきた。これは特に、北大の得意とする加速器利用分野とKEKの得意とする量子ビーム科学を融合による次世代を見据えた教育・研究の推進の一環である。令和6年度は、北大加速器施設の工事による長期シャットダウンのため実習は断念し講義のみの実施としたが、それを奇貨として全国に講義を開放することとし、対面とオンラインのハイブリッド型講義を行った。ハイブリッド型のスクールとしたことで、企業・研究所・海外からの受講を含め従来の倍の受講者となった。
- 代表者:加美山 隆 (北海道大学)
第4回 岩手コライダースクール
- 開催場所: 安比
- 開催期間:2025/02/24-2025/03/01
- Links: Home page
- 報告:
素粒子理論・実験問わず、国内外の主に大学院生、若手研究員を対象に、「4th Iwate Collider School (ICS2025)」 を2025年2月24日より6日間、岩手県八幡平市安比高原にて開催した。本スクールはKEK-IINAS-NXと岩手大学による共催で、岩手県立大学、岩手県ILC推進協議会からも援助を受け、2022年にスタートした。
KEK、東京大学からの講師に加えて、コライダー物理の分野で活躍する3名の講師を欧州から迎えた。国内からの12名の受講生に加えて、ドイツから1名、アジア諸国(インド、タイ、フィリピン、中国、香港、韓国)から13名の参加があり、本スクールの目的の一つである国際交流の場を受講生に提供することができた。受講生は、午前に講義を通してコライダー物理の基礎を学び、午後にパソコンを用いたチュートリアルでイベント生成シミュレーションを各自行った。このスクールでの交流が今後の国際共同研究へのきっかけとなることを期待して、ポスターセッション、立地を活かしたアクティビティー、また寝食を共にすることを通して参加者間の交流を最大限に促した。アジアでは少ないコライダー物理を学ぶ機会を提供し、現在進行中のLHC実験やILCを含む将来の加速器実験を牽引する若手育成に貢献できたと考える。 - 代表者:馬渡 健太郎 (岩手大学)
第7回東南アジア素粒子物理学スクール
- 開催場所:インドネシア ジョグジャカルタ
- 開催期間:2025/01/19-2025/1/24
- Links: Home page, photos
- 報告: 第7回東南アジア素粒子物理学スクール(PPSSEA2025)を、2025年1月19日から24日まで、インドネシア・ジョグジャカルタのUIN Sunan Kalijaga大学にて開催した。これは2年ごとに東南アジアの国で開催しているスクールで、KEKの講師が東南アジアの大学生・大学院生に素粒子関連の講義を行う。スクールには東南アジアの5ヶ国の43名が参加した。参加者は4日間の講義を受けたうえ、講義中に与えられた問題についてグループごとの発表を行った。素粒子物理に接する機会の少ない東南アジアの国の学生に、素粒子物理への興味を持ってもらうことができた。
- 代表者:西田 昌平 (KEK)
第19回弦と素粒子と宇宙論に関するKavliアジア冬の学校
- 開催場所:中国 三亜市
- 開催期間:2025/01/13-2025/01/22
- Links: Home page, photos
- 報告: この冬の学校では、毎年素粒子論と宇宙論の研究の第一線で活躍されている方々を講師としてお招きし、主に中国、インド、日本、韓国の大学院生を対象とした最先端のトピックスに関するわかりやすい講義をしていただいております。開催地はこの4か国を順番に回っており、今年は中国で開催されました。今年は9名の研究者による素晴らしい講義が行われました。それぞれの先生が1コマ1時間半の講義を4コマ行う形でスケジュールが組まれ、参加者たちは10日間にわたる充実した時間を過ごすことができました。日本からは8名の参加者があり、うち4名をIINASの予算でサポートすることができました。帰国した大学院生の方々からは、日頃なかなか詳しく聞けない最新の研究状況を、集中して学ぶことができてよかった、という感想が多く聞かれ、この経験が彼らの今後の研究にも大いに活かされるのものと期待されます。
- 代表者:西村 淳 (KEK)
SOKENDAI KEK Tsukuba/J-PARC Summer Student Program 2024
- 開催場所: KEK/東海
- 開催期間:2024/6/20-2024/9/13
- Links: Home page, photos
- 報告: 主に海外の大学生、大学院生が KEK つくばキャンパスまたは東海キャンパスに滞在し、 プロジェクトに参加して研究を行う機会を提供する SOKENDAI KEK Tsukuba/J-PARC Summer Student Program(KEKSSP) を開催した。世界 15 の国と地域から 21 名の学生 を受け入れた。参加者は「素粒子物理」「原子核物理」「物質・生命科学」「加速器」「先端 計測」などの中からプロジェクトを選び、4∼8 週間の期間、KEK や J-PARC で行われる 実験等で実習を実施した。実施期間の中盤には、滞在中の学生がつくばキャンパスに集ま り、学生の自己紹介や研究の中間報告に加え、総研大の紹介、素粒子物理などの講義や、 つくばキャンパスの施設見学を行った。本スクールで得た経験をもとに、総研大 (またはKEK/J-PARC のプロジェクトに参加している国内外の大学院) への進学につながることが期待される。
- 代表者:坂下 健 (KEK(総研大))
第8回中性子・ミュオンスクール
- 開催場所: 東海
- 開催期間:2024/12/09-2024/12/13
- Links: Home page, photos
- 報告: 2024年12月9日から13日にかけて、茨城県東海村にて第8回中性子・ミュオンスクールが開催されました。中性子・ミュオンビームを使った物質科学研究を学ぶため、日本を含む10ヵ国から合計31名の現地参加者が集まり、この分野で国際的に活躍されている研究者の方々を講師に迎えて各種実験手法のレクチャーを受けました。講義はオンラインでも配信され、各国から多数のアクセスがありました。期間中の後半では原子力科学研究機構内に設置された研究用原子炉JRR-3と大強度陽子加速器施設J-PARC物質・生命科学実験施設を用いて実習が行われました。残念ながらJ-PARCの方は施設の不調により実際の中性子・ミュオンビームを使うことはできませんでしたが、JRR-3の方は中性子ビームを使うことができ、両施設とも実際の装置に触れて実験方法や解析方法を学びました。スクール中は参加者が食事をともにして英語でコミュニケーションすることで相互理解を深め、議論の中で理解を深める姿が見られました。参加者の皆さんがこのスクールで学んだことを活かし、量子ビームを使った物質科学の分野で活躍し、JRR-3やJ-PARCにまたユーザーとして帰って来てくれることを期待しています。
- 代表者:大友 季哉 (KEK)
ビームダイナミクスと加速器技術のための国際スクール
- 開催場所:タイ チェンマイ
- 開催期間:2024/11/01-2024/11/09
- Links: Home page, photos
- 報告: 11月1日から9日に渡り、第7回ビーム力学と加速器技術に関する国際スクール(ISBA24)がタイ王国のチェンマイ大学を会場として開催された。106名の応募者から選ばれた日本、韓国、中国、台湾、インド、インドネシア、ドイツ、トルコ、そしてタイ(居住国ベース)からの学生64名が全課程を修了することができた。スクールでは、ビーム力学と加速器についての31コマの講義、10コマの実習、4コマの学生セッションが実施された。学生は加速器基礎に加えて、加速器におけるAIの利用、自由電子レーザーなどの最先端のトピックについても学んだ。実習ではElegant,Astra,CST,OPERAによる加速器設計にとりくみ、その成果は最終日の発表セッションにて発表された。学生セッションでは、学生自身の研究テーマを発表しあい相互理解を深めた。演習の発表セッション、学生セッションにおける優秀者は表彰された。スクール初日のレセプション、タイの歴史と文化への理解を深めた遠足(ワット・プラタート・ドイ・ステープ、チェンマイの旧市街)などで学生は相互の親睦を深め、順調にスクールは実施された。最終日には学生に修了証が手渡され、誇りと満足感で満たされた学生は帰途についた。
- 代表者:栗木 雅夫 (広島大学)
加速器科学インターンシップ
- 開催場所: つくば、東海
- 開催期間:2024/10 - 2025/03
- Links: Home page
- 報告: インターンシップの成果は報告書として提出を受けており、当該インターンシップ事業の ホームページ上で過去に実施したテーマとともに公開される。これらは本事業への応募を 検討する次代の学生に参照されるなど、有効に活用される。 公開用実施テーマ・成果報告書一覧
- 代表者:小関 忠 (KEK)
広島大学を中核とする加速器分野の人材育成体制の構築
- 開催場所: オンライン
- 開催期間:2024-09-05
- 報告: 加速器分野は、少数の大規模な加速器研究施設に人材や装置が集中しており、他分野と比較して、人材供給源となるべき大学などの研究室が非常に少ない。初等教育から高等教育の間の様々な機会に、加速器という一般にはあまりなじみのない分野を知ってもらい、将来の進路として目を向けてもらう努力が、分野の持続可能な発展のために不可欠である。本活動はこれを地域密着型で実施することを目指したものであった。広島大学の加速器研究室が地元の高専などと連携し、オンライン講演会の実施や県内での各種イベントへの出展、加速教育用VR教材の製作、機械学習の加速器分野への応用とそれを通じた人材育成など、多岐にわたる活動を実施してきた。このような活動を継続し定着させることで、加速器分野への人材誘導を通じてこの分野の発展に資することを目指した。
- 代表者:加藤 政博 (広島大学)
第18回サマーチャレンジ
- 開催場所: KEK
- 開催期間:2024/08/20-2024/08/28
- Links: Home page, photos
- 報告:
応募者数155名の中から選考された72名(うち1名は体調不良により不参加)によりサマーチャレンジが開催された。本スクールのプログラムは講義と演習から構成される。講義では村山斉氏による特別講演のほか、素粒子、原子核、宇宙、統計、加速器、放射線の講義が行われた。演習は素粒子・原子核関連実習、加速器関連演習、共通関連(放射線)演習、物性関連演習から、12テーマ程度の課題を行った。各班5-6名の小人数に分かれ、演習担当教官から直接指導が行われた。参加者は実習を通して装置作りから、実験、データ解析までを行った。大学における基礎実験技術の習得から一歩踏み出した、実際の研究を体感できるような演習プログラム行われた。つくばキャンパス・東海キャンパスの見学ツアーや、キャリアビルディングに関する座談会も行なわれた。
最終日には演習で学んだことを発表する成果発表会を行った。口頭発表やポスター発表では活発な質疑・応答が行われた。 - 代表者:齊藤 直人 (KEK)
高校生むけ素粒子サマーキャンププログラム 「Belle Plus」
- 開催場所:つくば KEK
- 開催期間:2024/08/06-2024/08/09
- Links: Home page, photos
- 報告: 全国から23名の高校生をつくば市の高エネルギー加速器研究機構(KEK)に招待し、最先端の最先端の研究現場を体験してもらう素粒子キャンプ 「Belle Plus」 を開催した。参加者の旅費・宿泊費をKEKが負担することで、住んでいる場所や家庭の経済状況にかかわらず、あらゆる生徒に機会を提供している。高校生たちは、素粒子物理学の入門講義や粒子加速器施設の見学に加えて、4つの班に分かれて専門的な内容のコース別素粒子実習を行い、得られた成果をプレゼンにまとめて最終日に研究発表を行った。また、キャリアパスについて大学院生TAに高校生が質問・相談できるセッションも実施した。参加者した高校生からは「興味があった素粒子についてかなり理解が進んだ」「普段は出会えない人と出会い、将来の生活やキャリアパスを具体的に想像できた」などの感想が得られた。
- 代表者:中山 浩幸 (KEK)
第13回ストレンジネス核物理国際スクール
- 開催場所: 和光
- 開催期間:2024/08/03-2024/08/08
- Links: Home page, photos
- 報告:
今回は、ホスト機関として東京大学理学系研究科物理学専攻および原子核科学研究センター(CNS)が加わり、これまでCNSが実施してきたCNS Summer School(CNS SS)と共同開催の形式で開催し、テーマとしてはこれまでのストレンジネス核物理の枠を大きく超え、ハドロン物理、天体物理はもちろんCNS SSでこれまで議論されてきた不安定核・低エネルギー核物理分野もカバーする広い内容へと拡張した。
6名の講師による講義、理研RIBF施設見学、参加学生、計65名による口頭・ポスター発表(Young Researchers’ Sesson, YRS)を行った。YRSで発表した参加学生には修了証を授与し、また講師・組織委員・シニア参加者の投票により選んだ優秀発表者11名を表彰した。
参加者は、講師・組織委員を含め、168名(うち対面参加者は120名)であった。 - 代表者:高橋 俊行 (KEK)
第七回粒子物理コンピューティングサマースクール
- 開催場所: KEK
- 開催期間:2024/07/29-08/02
- Links: Home page, photos
- 報告: 粒子物理コンピューティングサマースクールは、素粒子、原子核、宇宙線・宇宙物理分野における計算機利用技術を習得するための、大学院生を対象としたスクールです。第七回となった今回は、2024年7月29日から8月2日の五日間、KEKつくばキャンパスを会場に開催し、全国16大学26研究室から40名の大学院生が参加しました。講習内容は、プログラミング言語、統計解析ツール、多変量解析や深層学習を含む機械学習、GPUプログラミング、検出器シミュレーション、ソフトウェア開発ツールなどのソフトウェア関連技術と、計算機とネットワークの基礎、計算機クラスター、コンテナ技術、分散計算機環境、量子コンピューターなどのコンピューティング関連技術となっており、参加者はこれらを網羅的に学習しました。ATLAS実験のソフトウェア講習会も併設しています。最終日に行った実習成果発表会では、参加者全員がそれぞれ5分の持ち時間で、四日間に取り組んだ課題について工夫を凝らした発表を行いました。
- 代表者:田中 純一 (東京大学)
ベトナムニュートリノスクール2024
- 開催期間:2024/07/15-2024/07/26
- Links: Home page, photos
- 報告:
ニュートリノ実験の講義と実習を中心とした約 2 週間のサマースクールをベトナム中部の都市クイニョンで 7 月に開催した。2017 年から毎年開催しており 2024 年は 8 回目で ある。日本からの 5 人、ベトナムから 10 人、その他のアジアのから 5 人の学生を迎えた。 スーパーカミオカンデ実験と T2K 実験のメンバーが中心となってスクールを運営し、また 講師も務めた。22 コマの 90 分相当の講義とハードウェア実習、ソフトウェア実習、グル ープによる演習と発表を行った。
スクールは講義が中心であり、実際に実験装置を手にする時間が十分に取れない。こ れを解決するために、ハードウェア実習に特化した 1 週間のスクールの補講を 2025 年 3 月 に行った。2021 年度から始めた試みで、2024 年度は 4 回目である。15 人の学生を受け入 れ、シンチレータと光センサーを用いて宇宙線ミューオンの測定するエレクトロニクス演 習を行った。 - 代表者:大山 雄一 (KEK)
Asia-Europe-Pacific School of High-energy physics (AEPSHEP)
- 開催場所:タイ バンコク
- 開催期間:2024/06/12-2024/06/25
- Links: Home page, photos
- 報告: 国際スクールAEPSHEP2024 が、2024年6月12日から25日まで、タイ・バンコク近郊で、CERNとKEKの共催で開催された。これは、2年ごとに開催されている、アジア欧州大洋州の地域の博士課程の大学院生や若手研究者を対象としたスクールで、今回が6回目である。第一級の研究者による素粒子とその関連分野の講義や、グループに分かれての討論などが行われる、内容は充実したスクールであった。スクールには28の国の大学・研究機関の94名が参加した。日本の大学からも5名の学生と、グループ討論を指導するディスカッションリーダー1名が参加した。多くの国からの参加者がいることから、国際的な交流を行う良い機会が得られ、参加者からも好評であった。
- 代表者:西田 昌平 (KEK)
CERN サマー・スチューデント・プログラム 2024
- 開催場所:スイス CERN
- 開催期間:2024/06-2024/08
- Links: Home page, photos
- 報告: CERN Summer Student Programmeは、毎年世界各国から約200名の学生が参加し行われている。参加学生は2ヶ月程度CERNに滞在して特定の研究グループに所属し研究の補助をするほか、講義を受講し、最先端の素粒子原子核物理、加速器、計算機、放射線遮蔽技術等の最先端の分野を学ぶ。日本からの学生派遣は、KEK-CERN間の覚書に基づいて2004年から始まり、今回の4名を加えるとこれまでに87名を派遣している。プログラムに参加した多くの学生が有意義だったと報告しており、大学院を修了後、ポスドク等になって世界各地で活躍している。
- 代表者:戸本 誠 (KEK)
海外若手女性研究者受入事業(略称:アテナプログラム)
- 開催場所: つくば、東海
- 開催期間:2024/06 - 2025/03
- Links: Home page
- 報告:
ATHENA(アテナ)プログラムは、アジア太平洋地区の女性院生・若手研究者を日本の研究施設に受け入れる事業として、2013年にAAPPS (Association of Asia Pacific Physical Societies, アジア太平洋物理学会連合)が日本で開催されたことをきっかけに、日本物理学会の呼びかけで設立されました。KEKではこの招聘をきっかけに海外若手女性研究者受入事業(アテナプログラム)を行っており、途中コロナ下で交流が途絶えましたが、2024年度までに、22人の大学院生(博士課程)・若手研究者を受け入ました。参加者は各自の課題に真摯に取り組むだけでなく、KEKの研究開発の推進に貢献しています。
アジア圏では一部の地域を除いて、未だ女性研究者比率が低い傾向にあります。本事業により、KEKは教育・研究環境が相対的に恵まれている日本の研究機関として、アジア圏の研究機関との協力と交流を促進し、共同研究の機会を提供しています。KEKに滞在することで、最先端の実験施設、最新の研究成果、ツール、その他のリソースに容易にアクセスできるようにし、科学研究への女性の参画とキャリア形成を支援しています。 - 代表者:野尻 美保子 (KEK)
第12回高エネルギー物理春の学校2024
- 開催場所: 彦根
- 開催期間:2024/05/16-2024/05/18
- Links: Home page, photos
- 報告: 素粒子物理実験の面白さを伝え、大学院の学生同士の繋がり広げる目的で、第12回高エネルギー物理春の学校を開催した。講師を含むスタッフ13名、19機関から83名の学生受講者が参加した。ほぼ修士1年生の参加であったが、修士2年生が7名、博士学生が5名参加した。女性比率は16%だった。講師による7個の初学者向けの講義と、学生による16個の口頭発表と63個のポスター発表、学生によるパネル討論があった。講師も3名が春の学校のOBによるものだった。講義内容は、素粒子理論、検出器、宇宙背景放射実験やニュートリノ実験など、基礎から実験のフロンティアまでカバーした。学生からの活発な質疑があり、講義のあとも講師との議論が続いた。学生の発表における質疑では、司会が捌ききれないほどの挙手があり、学生の積極的な参加が見られた。ポスター発表では、学生同士の活発な議論が深夜まで続き、交流が深まった。パネル討論では、学生が素粒子実験を志した動機やキャリアパスについて議論した。学生が講義により素粒子実験の基礎を学ぶことができ、また多くの仲間を得てくれた。実施後の学生のアンケート回答での評価も高く、今後もこのような機会を提供していきたい。
- 代表者:南條 創 (大阪大学)
TYLスクール:理系女子キャンプ2024
- 開催場所: つくば
- 開催期間:2024/04/03-2024/04/04
- Links: Home page
- 報告:
「TYLスクール:理系女子キャンプ」は、女子高校生がKEKつくばキャンパスで、科学実験やパネルディスカッション、施設見学ツアーなどへの参加を通じて、理系への進路について考えてもらおうという企画です。2024年度は、全国から応募した30名の参加者に対し、霧箱を使った科学実験、外国人を含む第一線で女性科学者による講義、加速器体験ツアー、女子大学院生との交流などのプログラムを実施しました。
参加者アンケートでは、同じ興味を持つ同年代の参加者との共同作業、女性研究者の経験談、加速器実験に携わるKEK研究者とのふれあい等によって、研究の楽しさと奥深さ、国際性の重要さについて学ぶことができた、これまであまり接点がなかった女子大学院生との交流を通じて、進路決定や理系の学部での勉強や大学院での研究活動に具体的なイメージを持つことができた、という感想が集まり、本課題は、参加者が研究者としての将来像をポジティブに描く機会となりました。
KEKトピックス記事 - 代表者:野尻 美保子 (KEK)
高専で作る小型サイクロトロン加速器教材の制作
- 報告: 世界的にもユニークな教育システムとして注目されている高専において、世界でも類を見ない「学生自らが加速器を製作する」取り組みが進められています。小山・長野・豊田の3高専では、小型サイクロトロン加速器の開発に取り組み、電子ビームの観測にも成功しました。さらに、加速の原理を初学者にもわかりやすく学べる「加速器おもちゃ」の製作や展示も行い、一般向けイベントでは来場者から好評を得ています。現在は沖縄・群馬高専でも新たな活動が始まり、参加校は全国に広がっています。学生自身が製作手順をまとめたマニュアルも整備され、他校での活用が進んでいます。こうした活動は学会誌でも紹介されるなど注目を集めており、段階的に学べる教材の開発や、海外教科書の翻訳も進行中です。学生が自ら加速器科学に触れ、学び、社会とつながる実践的な教育として、今後の展開が期待されています。
- 代表者:大谷 将士 (KEK)
インクルーシブ素粒子教材の開発
- 報告:
視覚障害者向けの素粒子教材を開発した。開発した主な教材は、巨大な素粒子実験装置を触って理解するための縮小模型と、音で聴く小型の放射線検出器である。前者はKEK機械工学センターの3Dプリンタで制作し、後者は加速キッチンに所属する学生メンバーが開発を担当した。視覚障害の当事者や視覚障害者教育に携わる専門家を訪問し、教材を試用してもらってフィードバックをいただき、それをもとに教材の改良を重ねた。特に、ダイアログ・イン・ザ・ダーク(DID)との協働を通じて、DIDに所属する3名の全盲のアテンドの方々から多くの有用なアドバイスを提供していただいた。
完成した教材を用いて、筑波大学附属 視覚特別支援学校において、全盲の高校生への出前授業プログラムを3月に実施することができた。 - 代表者:中山 浩幸 (KEK)
いつでもどこでも素粒子入門
- 報告: 素粒子を専門とする教員がいない大学からの大学院進学者は,基礎講義や実験経験が不足し素粒子物理学や実験技術知識が不足しがちである。独学や先輩からのノウハウが欠けたまま研究を始めることも多い。素粒子物理や実験技術の基礎を学べる動画教材を提供することで、学部高学年・修士1年生がオンラインで,時と場所を選ばずに繰り返し学べるようにすることが本教材の目的である。集中して効率的に学べるように,動画やテーマによって分けた15分程度のものを多数用意する。本年度,まず体系的な学習をするためのテーマリストの策定から始めた。教材作成の共通ルール,動画作成のノウハウの蓄積に努めた。10名の教員で動画を分担して作成し,YouTubeでの公開,ホームページでの広報を見越して,内部公開版を準備した。最終目標の75動画に対して,まずは基礎的なテーマに関する9動画の作成が完了した。現在内部レビュー用にYoutubeの限定公開を行っている。
- 代表者:陣内 修 (東京工業大学)
低温温度領域を体感出来る科学おもちゃ(パルス管冷凍機)の製作
- 報告: 物が冷える過程を体験出来る科学おもちゃを製作し、一般公開において展示する事で、実際に物を冷やす実験を体験して貰える。製作したのは、パルス管冷凍機と呼ばれている、一般的な装置で、加速器の研究所の中や、病院において実際に利用されている装置である。中の構造が一目で確認出来る様に、透明な管を使って構成してあり、物を冷やす過程を体感出来る様に、簡単な手動弁2つの操作だけで、運転出来る構造になっている。常温から始めて、数分間手動弁の操作を繰り返すだけで、はっきりと物が冷えている事が実感出来るが、冷凍機本体には、全く機械的に動く部品は全く含まれて無い。この不思議な装置を実際に操作する事で、低温への興味や関心を広く持って貰う事を目的としている。
- 代表者:清水 洋孝 (KEK)
VR教育加速器の開発とVR加速器博物館の立ちあげ
- 報告: 2023年度からソーシャル・メタバース(VR)・プラットフォームであるVRChatの中に「メタバース加速器博物館(MAM)」の枠組みを作成した。これにより全ての展示物が全世界に一挙に公開でき、VR-メタバースを使った加速器教育・広報にこれまで考えられなかった展開が考えられるようになった。2024年度は多数の展示室への入口のある「MAM玄関ホール」と、「KEK教育加速器(KETA)展示室」を作成した。KETAに関しては、本物の加速器では外観しか見えないが、その内部構造まで見ることができるようになった。さらに本格的なビームシミュレーションの結果を元にしたビームの振る舞いも見られる。これは世界中に公開されており、すでに5千人前後の訪問があった。また、博物館を拡張するため、北海道大学の電子加速器、広島大学の愛知シンクロトロン加速器、筑波大の6MVタンデム加速器、広島大のHiSORその他のVRモデルの作成を開始した。
- 代表者:古坂 道弘 (高エネ機構)
2023年度
岩手コライダースクール
- 開催場所:日本 安比
- 開催期間:2024/02/26-2024/03/02
- Links: Home page, photos
- 報告:
素粒子理論・実験を問わず主に大学院生、若手研究員を対象に、国際スクール「IwateColliderSchool2024」を2024年2月26日より6日間、岩手県八幡平市安比高原にて開催した。KEK-IINAS-NXと岩手大学による共催で、岩手県立大学、岩手県ILC推進協議会からも援助を受け、2022年、2023年に続く3回目の開催となった。今回は完全対面形式で、受講者数を25名から30名に拡大、コライダー物理の一線で活躍する4名の講師を欧州から招待して開催した。国内のみならず、ドイツ、インド、中国、韓国からの参加もあり、本スクールの目的の一つである国際交流の場を受講生に提供することができた。
受講生は、午前に講義を通してコライダー物理の基礎を学び、午後にパソコンを用いたチュートリアルでイベント生成シミュレーションを各自行った。このスクールでの交流が今後の国際共同研究へのきっかけとなることを期待して、ポスターセッション、スキー等のアクティビティー、また寝食を共にすることを通して参加者間の交流を最大限に促した。アジアでは少ないコライダー物理を学ぶ機会を提供し、現在進行中のLHC実験やILCを含む将来の加速器実験に貢献する若手育成の役割を果たせたと考える。 - 代表者:馬渡 健太郎 (岩手大学)
第5回アジア加速器用超伝導・低温技術スクール
- 開催場所:日本 つくば市
- 開催期間:2024/01/28-2024/02/05
- Links: Home page, photos
- 報告: 2024年1月28日から2月5日まで、高エネルギー加速器研究機構つくばキャンパスで第5回アジア加速器用超伝導・低温技術スクールを開催した。受講者は40名(日本機関所属8名、外国機関所属32名)、講師は18名(日本機関所属13名、外国機関所属5名)で、その他のスタッフ3名を含めて総勢61名となった。受講者と講師の国籍は、日本以外では、中国、インド、タイ、韓国、台湾、ネパール、フランスおよびベラルーシの8か国であった。スクールの内容は、超伝導加速器用超伝導空洞や超伝導磁石、低温工学に関する18の講義と、高周波空洞、高温超伝導体の磁気浮上、低温工学関係の3種類の実習を行った。また、実習の一環としてSuperKEKBの日光ヘリウム冷凍機とBelle II検出器、およびSTFの見学を行った。このスクールによって、超伝導加速器の発展と人材育成、国際協力に大きな寄与ができた。また、アジア地域の国々から若手の研究者・技術者や学生・大学院生が交流を深め、国際的な人的ネットワークが形成された。
- 代表者:仲井 浩孝 (KEK・加速器)
第7回中性子・ミュオンスクール
- 開催場所:日本 東海村
- 開催期間:2023/12/18-2023/12/22
- Links: Home page, photos
- 報告: 物質に対する透過力が大きい特徴を活かし、自動車のエンジン等工業製品の透過観察や、ピラミッドや古墳の内部観察等を非破壊で観察できるプローブとして幅広く利用されている中性子やミュオンであるが、その利用研究分野はまだまだ拡大の余地が大きい。中性子およびミュオン科学の裾野や利用分野の拡大や人材育成のため、大学院生や若手研究者を対象としてThe 7th Neutron and Muon Schoolを開催した。今年度のスクールでは、国内外からの17名の実習生と105名のオンライン聴講生を迎え、海外を含む講師陣からの講義を通じて中性子・ミュオン科学の基礎を学ぶとともに、茨城県東海村の大強度陽子加速器施設J-PARCと研究用原子炉JRR-3の中性子、ミュオン実験装置を用いて実習を行った。実習生はスクールのプログラムが進むにつれて実習生同士や講師、スタッフとのコミュニケーションを深め、最終日には実習の成果を自信を持って発表しスクールは終了した。事後アンケートでは「スクールを楽しむことができた」「今後に活かしたい」等の前向きなコメントを多くいただいた。今後の当該分野を支える人材への成長を期待したい。
- 代表者:大友 季哉 (KEK・加速器)
The 12th International School for Strangeness Nuclear Physics (SNP School 2023)
- 開催場所:日本 東海村
- 開催期間:2023/12/11-2023/12/15
- Links: Home page, photos
- 報告: 今回で12回目となるスクールの参加者は、講師・組織委員合わせて90名、そのうち20名が海外からの参加で、対面参加者は60名(うちが海外からは8名)であった。 5名の研究者による原子核物理(原子核、ハドロン、高エネルギーQCDの物理)、素粒子物理、天体核物理をテーマとした講義を行った。 また、スクール参加学生39名による口頭発表とそのうち現地参加した31名がポスター発表も行った(Young Researchers Session, YRS)。YRSの発表は、講師・組織委員で採点をして優秀者7名を表彰した。 さらに~30名がJ-PARCのハドロン実験施設,ニュートリノ実験施設、物質・生命実験施設の各実験施設を見学した。
- 代表者:高橋 俊行 (KEK・素核研)
第17回サマーチャレンジ
- 開催場所:日本 つくば市
- 開催期間:2023/08/18-2023/08/27
- Links: Home page
- 報告:
- 代表者:齊藤 直人 (KEK・素核研)
The 6th International School on Beam Dynamics and Accelerator Technology (ISBA23)
- 開催場所:韓国 Pohang
- 開催期間:2023/08/03-2023/08/12
- Links: Home page, photos
- 報告: 8月3日から12日の三日間、韓国の浦項加速器研究所を会場として第六回目の国際加速器スクールISBA24が開催されました。ISBAは2018年から広島県東広島市を会場として開催されてきましたが、今回が初めての海外で開催です。韓国、日本をはじめ、中国、台湾、インド、そして今回から初参加のタイから学生85名が集いました。スクールでは加速器理論、技術、加速器を利用した科学研究および応用についての講義が行われ、学生は基礎科学から医療、産業で幅広く利用されている最先端の研究装置である粒子加速器の全てについて学びました。学生は粒子加速器シミュレーションにチームで取り組み、他のチームより高い性能を実現しようと日夜努力を重ねました。その成果は最終日に発表され、優秀なチームは表彰の栄誉をうけました。浦項放射光、X線自由電子レーザー、重イオン加速器KOMACへの訪問、さらに慶州の仏国寺そして慶州国立博物館への遠足も実施され、学生は実際の加速器研究の現場と、地域の文化と歴史に触れるという貴重な体験もしました。
- 代表者:栗木 雅夫 (広島大学)
高校生のための素粒子サイエンスキャンプ Belle Plus 2023
- 開催場所:日本 つくば市
- 開催期間:2023/08/01-2023/08/04
- Links: Home page
- 報告: 全国から24名の高校生をつくば市の高エネルギー加速器研究機構(KEK)に招待し、最先端の最先端の研究現場を体験してもらう素粒子キャンプ 「Belle Plus」 を開催した。参加者の旅費・宿泊費をKEKが負担することで、住んでいる場所や家庭の経済状況にかかわらず、あらゆる生徒に機会を提供している。高校生たちは、素粒子物理学の入門講義や粒子加速器施設の見学に加えて、4つの班に分かれて専門的な内容のコース別素粒子実習を行い、得られた成果をプレゼンにまとめて最終日に研究発表を行った。また、キャリアパスについて大学院生TAに高校生が質問・相談できるセッションも実施した。キャンプに参加した参加者からは「ちいさな素粒子と大きな宇宙がつながっていることに感動した」「同じ興味を持つ友達がたくさんできた」「実際の研究活動を体験でき、進路を考えるうえで参考になった」という感想が得られた。
- 代表者:中山 浩幸 (KEK・素核研)
第六回粒子物理コンピューティングサマースクール
- 開催場所:日本 つくば市
- 開催期間:2023/07/31-2023/08/04
- Links: Home page
- 報告: 粒子物理コンピューティングサマースクールは、素粒子、原子核、宇宙線・宇宙物理分野における計算機利用技術を習得するための、大学院性を対象としたスクールです。第六回となった今回は、2023年7月31日から8月4日の五日間、KEKつくばキャンパスを会場に開催し、全国14大学26研究室から40名の大学院生が参加しました。講習内容は、プログラミング言語、統計解析ツール、多変量解析や深層学習を含む機械学習、GPUプログラミング、検出器シミュレーション、ソフトウェア開発ツールなどのソフトウェア関連技術と、計算機とネットワークの基礎、計算機クラスター、コンテナ技術、分散計算機環境、量子コンピューターなどのコンピューティング関連技術となっており、参加者はこれらを網羅的に学習しました。ATLAS実験、Belle II実験のソフトウェア講習会も併設しています。最終日に行った実習成果発表会では、参加者全員がそれぞれ5分の持ち時間で、四日間に取り組んだ課題について工夫を凝らした発表を行いました。
- 代表者:田中 純一 (東京大学)
Vietnam School on Neutrinos 2023
- 開催場所:ベトナム Quy Nhon
- 開催期間:2023/07/18-2023/07/28
- Links: Home page, photos
- 報告: ニュートリノ実験の講義と実習を中心とした約2週間のサマースクールをベトナム中部の都市クイニョンで7月に開催した。2017年から毎年開催しており2023年は7回目である。日本からの6人、ベトナムから11人、その他のアジアのから9人の学生を迎えた。スーパーカミオカンデ実験とT2K実験のメンバーが中心となってスクールを運営し、また講師も務めた。20コマの90分講義とハードウェア実習、ソフトウェア実習、グループによる演習と発表を行った。 スクールは講義が中心であり、実際に実験装置を手にする時間が十分に取れない。これを解決するために、ハードウェア実習に特化した1週間のスクールの補講を2024年3月に行った。2021年度から始めた試みで、2023年度は3回目である。14人の学生を受け入れ、シンチレータと光センサーを用いて宇宙線ミューオンの測定するエレクトロニクス演習を行った。
- 代表者:大山 雄一 (KEK・素核研)
史料を科学する
- 開催場所:日本
- 開催期間:2023/07-2024/03
- 報告: 本事業は、物理化学的手法によって古文書料紙の成分分析を行い、非碳壊調査のための新たな計測技術の開発・実用化を進め、古文書料紙の総合的な科学研究を進展させること、また、保存・修復等に携わる人材の育成、および各種歴史資料を通した地域社会との連携・協働の新たな展開をはかることを目的とする。令和5年度は、料紙サンプルを対象として3次元X線顕微鏡(X線CT)やフーリエ変換赤外分光分析(FT-IR)等による成分分析(非破壊)を行った。x線CTの分析では、実験製作した糊付け和紙や水害等によって固着・劣化・分解の状態となった史料の剥片について、文字や内部構造の識別、繊維の形態の測定を行った。FT-IRの分析では、関義城『古今紙漉紙屋図絵』の見本紙50点、現代の青雁皮紙1点の合計51点に対して実施した。なお、FT-IRの結果を用いた統計解析を行ったところ、紙質の特徴を明瞭に識別できることが判明し、国内外の学会・研究会等で成果の報告を行った。
- 代表者:高島 晶彦 (東京大学)
CERNサマー・スチューデント・プログラム2023
- 開催場所:スイス Geneva
- 開催期間:2023/06-2023/09
- Links: Home page
- 報告: CERN Summer Student Programmeは、毎年世界各国から約200名の学生が参加し行われている。参加学生は2ヶ月程度CERNに滞在して特定の研究グループに所属し研究の補助をするほか、講義を受講し、最先端の素粒子原子核物理、加速器、計算機、放射線遮蔽技術等の最先端の分野を学ぶ。日本からの学生派遣は、KEK-CERN間の覚書に基づいて2004年から始まり、今回の4名を加えるとこれまでに83名を派遣している。プログラムに参加した多くの学生が有意義だったと報告しており、大学院を修了後、ポスドク等になって世界各地で活躍している。
- 代表者:花垣 和則 (KEK・素核研)
Sokendai KEK Tsukuba/J-PARC Summer Student Program 2023
- 開催場所:日本 つくば市、東海村
- 開催期間:2023/06-2023/08
- Links: Home page, photos
- 報告: 本プログラムは、意欲の高い学生にKEKの実験等を実体験してもらうことで、KEKや総研大に興味を持ってもらい、総研大への進学や将来のKEKとの国際連携の中心となる研究者への育成を目指すことを目的としている。コロナ禍のための休止期間を経て久しぶりに開催された今回は、208名の学部・修士課程相当の学生から応募があり、18名を採択した。参加者は、KEKのつくば又は東海キャンパスに4-8週間滞在し、受入れ教員のもとで研究を行った他、J-PARC、Belle II、 Photon Factory などの研究施設の見学などを行った。参加者のうち1名が総研大国費留学生選抜(令和6年入学者向け)に出願、素粒子原子核コースを受験するという直接的な効果のほか、KEKや実験プロジェクトに興味を持ってもらえたということで一定の成果が得られた。今回、コロナ禍明けで希望者が多かったというのを考慮しても、応募者は非常に多く、このプログラムが諸外国にも認知されてきたといえる。
- 代表者:西田 昌平 (KEK・加速器)
第11回高エネルギー物理春の学校2023
加速器科学インターンシップ
- 開催場所:日本 つくば市、東海村
- 開催期間:2023/05/01-2024/03/31
- Links: Home page
- 報告: インターンシップの成果は報告書として提出を受けており、当該インターンシップ事業のホームページ上で公開される。これらは本事業への応募を検討する学生に参照される等有効活用される。 公開用実施テーマ・成果報告書一覧
- 代表者:小関 忠 (KEK・加速器)
TYLスクール:理系女子キャンプ2023
- 開催場所:日本 つくば市
- 開催期間:2023/04/03-2023/04/04
- Links: Home page
- 報告: 本スクールでは、参加する30名の女子高校生に対し科学実験、外国人を含む科学分野の第一線で活躍する女性研究者による講義、大型実験施設の見学、女子大学院生とのパネルディスカッション・懇談などのプログラムを実施しており、同じ興味を持つ同年代の女子に出会え、理系大学の学部での勉強や大学院での研究活動に具体的なイメージが持て、また、海外からの講師に接することにより世界にも目を向ける意識が芽生えることなど、期待した成果は得られていると感じている。KEKトピックス記事
- 代表者:野尻 美保子 (KEK・男女参画)
タンデム静電加速器に関するVR教材の開発
- 開催場所:日本 つくば市
- Links: , photos
- 報告: 令和4年度から継続して加速器科学国際育成事業 (IINAS-NX)の支援を受けて、KEKと連携して筑波大学が所有するタンデム静電加速器について、VRゴーグル等で疑似体験できる環境を整備し、VR教材の改良を行った。具体的には、加速器の詳細な3D図面の作成やVRゴーグルを装着した人自身で加速器を学ぶことができるようにするための説明表示を新たに加えた。また、所有する6個のVRゴーグルを同時に画面共有することができるような環境を構築した。VR技術の改良により、加速器のVR教材としての効果が上がり、VRゴーグル使用者の加速器への興味・関心や理解度の向上につながった。令和5年度は、高校生の大学施設見学、技術職員の研修会等において、580名の参加者が加速器に関する学習・研修に利用した。
- 代表者:笹 公和 (筑波大学)
大学・高専連携による加速器分野での人材育成・技術開発・分野融合の加速
- 開催場所:日本
- 報告: 広島大学と地域の高専(呉工業高専、広島商船高専)を中核とする加速器研究教育拠点を形成し、KEKとの密接な連携・協力のもと、啓蒙活動等を通じて加速器関連分野へ人材を誘導し、大学加速器施設の高度化、先端加速器技術開発、量子ビーム利用の分野融合的応用を進める中で、基礎から最先端まで一貫した加速器科学教育環境を構築し人材育成を促進することを目指して活動を行った。2023年度は、KEK-day「加速器を楽しもう」と題して高専生・大学生向けのオンライン講演会を実施した他、広島大学の放射光施設において地域の中高生を対象とする施設見学・オンライン出前授業などに取り組んだ。VRを活用した加速器教育・啓蒙活動用コンテンツの作成、加速器運転の省力化を目指した機械学習の加速器制御への応用に関する研究に高専生、大学院生が参加し、卒業研究、修士論文のテーマとして取り組んだ。
- 代表者:加藤 政博 (広島大学)
茨城大学-KEK 加速器科学総合人材育成プログラム
- 開催場所:日本
- 報告: このプロジェクトの援助によって茨城大学-KEK dayを実施し、茨城県東海村にあるJ-PARCやつくば市に所在するフォトンファクトリーの見学を茨城大学の学部生や大学院生を対象に行った。さらに「量子ビームで歴史探検!」というタイトルの講演会も実施した。今年度は、茨城大学理学部、工学部、理工学研究科だけでなく、人文社会科学科の学部生も見学に参加して、量子ビーム研究の重要性について理解した。さらに、大学院理工学研究科専門科目を構成しているマルチ量子ビームプログラムを実施したほか、「電子の兄弟」のような素粒子であるミュオンの加速器要素技術の開発に関する研究を行い、多くの学術誌論文をKEKと共同で出版したほか、大学院生を中心に素粒子物理実験に関する学会の賞を受賞した。この技術が開発されれば、物体や建造物などの透視が可能になる。茨城県東海村と共同で「宇宙線ミュオンで古墳を透視プロジェクト」を開始し、古墳内部調査のためのミュオン検出器を製作した。
- 代表者:森 聖治 (茨城大学)
海外若手女性研究者受入事業(アテナ)プログラム
- 開催場所:日本 つくば市
- Links: Home page
- 報告:
- 代表者:野尻 美保子 (KEK・男女参画)
空間的障害を乗り越えた加速器科学教育・研究体制の構築
- 開催場所:日本 札幌市
- 報告: 北海道大学(北大)と高エネルギー加速器研究機構(KEK)は10年来加速器利用分野で連携し加速器科学の教育・研究事業を進めているが、北海道と茨城という空間的な障害は埋めがたいものがあり、本プログラムではこうした空間的な障害を小さくするべく、デジタル技術を駆使して、特に北大の得意とする加速器利用分野とKEKの得意とする量子ビーム科学を融合した次世代を見据えた教育・研究を推進した。令和5年度は、総合大学であるという北大の特徴を活かし加速器利用へのキャリアパス紹介と北大加速器施設の実地見学、VRを使った加速器内現象の可視化を交えた体験型の北大・KEK-dayをハイブリッド型で開催し地方の高専生まで含めた幅広い層に加速器科学をアピールするとともに、大学および大学院学生に対する加速器科学講義を実施し、総合大学を構成するグローバルな人材に対する育成教育を継続実施した。さらに北大の加速器のVRモデルを構築し、KEKの3Dモデル化VR教材への統合を検討した。
- 代表者:加美山 隆 (北海道大学)
updated: 2026-01-06