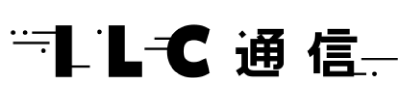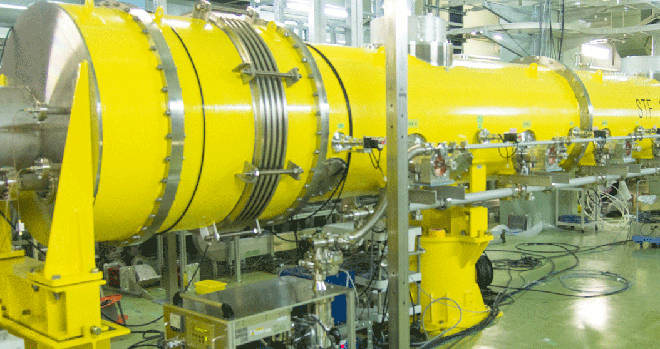光の正体は科学の歴史の中で大きな謎でした。時に粒子であると考えられたり、何かが伝える波であると考えられたり。19 世紀の半ばに整えられた電磁気学の理論「マックスウェルの方程式」が、電気の力や磁気の力のもととなる電場と磁場が、あざなえる縄のようになって空間を伝わる「電波」の存在を明かしました。そしてその電波の速度が、当時ようやく正確に測れるようになった光の速度と一致していたことから、光の正体は電波であると結論づけられます。
しかし、1905 年にアインシュタイン博士が、光が光源から発せられて広がっていくときに、そのエネルギーは連続して広がっていくのではなく、光の波長に反比例した「かたまり」で伝わっていくという論文を発表します。エネルギーがとびとびの値をとるエネルギーの最小単位のことを「エネルギーの量子」と呼びますが、アインシュタインは光エネルギーの最小単位のことを「光量子」と呼びました。そして、この光量子は最小単位として分割されることなく運動し、発生するときも吸収されるときもそのかたまりのままで行われるとの仮説を提案したのです。この仮説により当時知られるようになった光電効果という金属に光が当たったときに電子が飛び出してくる現象の様子を正確に説明できると指摘しました。
アインシュタイン博士はこの光量子仮説により1921 年にノーベル物理学賞を受賞します。そして1924 年、光量子が存在する直接的な証拠となる現象が発見されます。光が電子と衝突して電子を跳ね飛ばす現象、コンプトン散乱現象です。このとき電子にあたって跳ねたあとの光自身の波長が長くなることが観測されました。これも光が波であるとすると説明がつかず、光が光量子としてドスンとぶつかるという考えでしか説明がつかないことがわかったのです。それ以来光は「光子」という素粒子であると考えられるようになっていきます。そして、マックスウェルの方程式も光子の運動を扱う「量子電気力学の方程式」へと進化します。