 加速器図鑑
加速器図鑑 加速器図鑑❹ ダンピングリング
ILCのダンピングリング完成予想図 ずらりと並んだ磁石が粒子の向きを整える ©︎Rey. Hori
ILCは「直線型衝突加速器」ですが、実はその中央に周長3.2キロメートルの円形加速器があります。この円形加速器は「ダンピングリング」...
 加速器図鑑
加速器図鑑 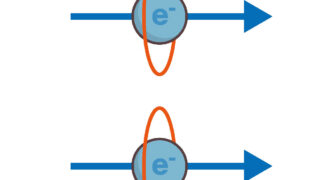 ILCの物理学
ILCの物理学 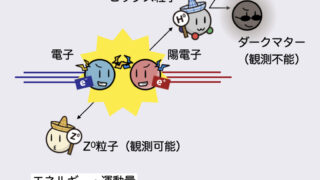 ILCの物理学
ILCの物理学  加速器図鑑
加速器図鑑 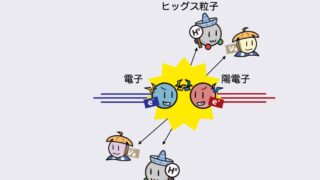 ILCの物理学
ILCの物理学  加速器図鑑
加速器図鑑 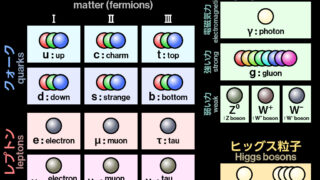 ILCの物理学
ILCの物理学 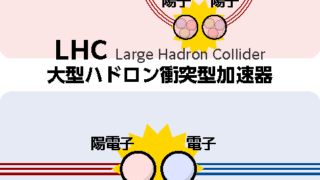 ILC Q&A
ILC Q&A 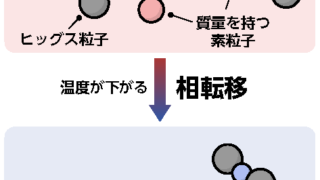 ILCの物理学
ILCの物理学  ILCのポテンシャル
ILCのポテンシャル