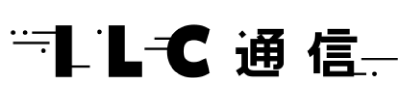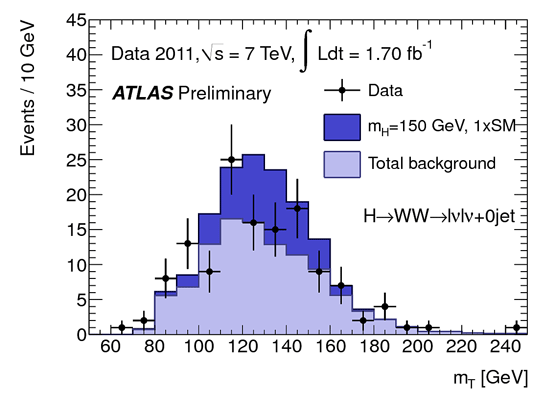ATF加速器トンネル中で電磁石などの位置測量・調整作業が進められている。
3月11日の東日本大震災発生以降、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の先端加速器試験施設(ATF)では精力的に被害状況確認作業が続けられて来た。ATFでは6月3日に行った試験で、ATF2ビームライン最下流までビームが通ったことが確認された。これはATFの将来の運転再開に向けて明るいニュースだ。
ATFは、国際リニアコライダー(ILC)の実現に必須となる高度な技術の開発と実証を行う試験加速器で、「極小」で「平行度の高い」ビームの生成を目指した研究開発が進められている。
ILCは衝突型加速器。加速した電子ビームと陽電子ビームを正面衝突させる。加速される「ビーム」は非常に薄いリボンのような形で、200億個の電子や陽電子から形作られている。ビームのサイズを小さくすれば、電子や陽電子の密度が高くなり、電子と陽電子の衝突の頻度が上がる。次世代加速器では、非常に高い衝突頻度を目指しているため、要求されるビームのサイズは非常に小さい。そのサイズは衝突点付近で、高さ5ナノメートル(ナノメートル=100万分の1mm)幅300ナノメートルという極小ビームだ。「平行度が高い」とは、ビームの中の粒子の進行方向揃っているために、遠くへ行ってもほとんど広がらないことを指す。ATFでは、これまでのビームより約100倍も平行度の高いビームをつくることが可能だ。この非常に小さく平行度の高いビームを開発研究に利用することができるATFは、世界中の研究者にとって魅力的な施設である。震災前には、外国人研究者が常時ATFに滞在していた。
ATFやATF2ビームラインには、世界各国で作られた様々な装置も組込まれており、今回の震災でそれらの装置にも被害が出ていた。震災から2ヶ月経った5月中頃から、外国人研究者たちが被害確認と修復作業のために次々とATFに戻り始めた。
まず、米SLAC国立研究所(SLAC)から2名の研究者がATFを訪れた。そのうちの1名の研究者は震災当日にもATFで作業にあたっていたが、いったん米国に帰国。今回再来日し、2週間滞在してSLACがロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校(RHUL)と共同で開発したビーム位置モニターシステムと、ATF2ビームラインの磁石ムーバーの修復作業を行った。
6月に入ると、英国からRHULの研究者が、非常に高い分解能でビームの位置を測定する「空洞型ビーム位置モニター」と呼ばれる装置の立ち上げを行うためにATF入りした。6月後半からは、フランス線形加速器研究所(LAL)の研究者が「偏極陽電子」を生成するための装置である「4ミラーキャビティ(4枚鏡・光蓄積空洞)」の確認および立ち上げ作業に、続いて4名の英オッフォード大学の研究者グループが、ナノメートルレベルでのビーム制御を行う「FONTシステム」の確認のために来日し、各装置の確認・修復作業が急ピッチで進められている。
しかしATF国際研究チームスポークスパーソンの照沼信浩氏は「まだまだやることはたくさんあります」と、語る。ビームの品質を震災前のレベルまで戻すためには、様々なパラメータの確認や機器の調整など、しなければいけない作業が山積している。ビームの試験運転が停止される夏期には、数多くの確認・調整作業が予定されている。