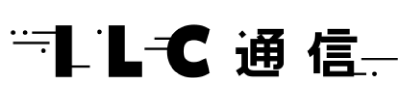核力に関して理論的な考察を行い「中間子」の存在を予測した湯川秀樹博士は、1949 年に日本人として初のノーベル賞を受賞されました。中間子は今ではクォークと反クォークが強く結びついた粒子であることがわかっています。研究者はそれ以上細かくできない粒子のことを素粒子と呼ぶので、中間子は素粒子ではないことになります。一方、高校の教科書では、「原子核より小さい粒子のことを素粒子と呼ぶ」としており、この定義によれば原子核を構成する陽子や中性子も、また中間子も素粒子ということになります。
湯川博士の理論は「力は粒子の交換により生じる」という考え方を初めて提唱したもので、それが今ではすべての力に適用される基本的な考え方となっています。
原子核は陽子と中性子から成り立っています。陽子や中性子の間には、距離が一千兆分の1メートル以下ではとても強く働きますが、それ以上離れると急激に弱くなる力、「核力」が働いています。
湯川博士は核力のこの性質を、未知の素粒子の交換として説明しました。例えば、陽子は正の電荷を持つ粒子を放出して中性子になり、その粒子を受け取った中性子は陽子に変化します。量子力学における時間とエネルギーの不確定性原理によれば、中性子より質量がやや小さい陽子が、非常に短い時間であればエネルギー保存則を破って質量を持った粒子を放出し、中性子がそれを受け取ることができます。湯川博士は核力が働くわずかな距離から粒子が交換される時間を割り出し、不確定性原理を使うことで未知の粒子の質量を電子の200 倍程度と予測しました。電子と陽子の中間の質量を持つことから、新粒子を「中間子」と呼びました。
1947 年、写真乾板を使った宇宙線の観測で電子の質量の約300 倍の粒子が見つかり、これが湯川博士の予測した中間子であることが確認されました。