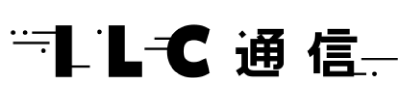※この記事は、CERN Courier 2021年1月/2月号に掲載された記事の翻訳記事です。
国際リニアコライダー(ILC)は、第一段階を重心系エネルギー250 GeVのヒッグスファクトリー(以下、「ILC250」)とする計画中の電子陽電子型線形加速器である。電子ビームと陽電子ビームの縦偏極が可能であり、将来の加速器の拡張として500GeVから1TeVまで、さらにはそれ以上のエネルギーへの拡張の可能性もある。さらに、ILCのビームは時間構造が特徴的であるため(0.554ms間隔の1312個のバンチが非常に短時間に次々に衝突することが5 Hz周期で繰り返される)、測定器に必要な読み出し速度と放射線耐性の性能はLHCと比較してはるかに低い。これによりILC測定器では、低質量の飛跡検出器と高精細センサーが利用でき、かつてないジェットエネルギー分解能が得られる。また、データ量は毎秒数GB程と想定され、トリガーをもちいず全ての衝突を記録することが可能である。
ILC250の第一目標はヒッグス粒子の精密測定であるが(参照:Targeting a Higgs factory)、それを最大限利用するためには、標準理論を検証するための他の観測量についても測定の更新が必要となる。とくにILC250は次の三つを切り拓く。(1)250GeVでのゲージボゾン対生成とフェルミオン対生成。(2)光子の事前放射により重心系エネルギーが実質約91.2GeVに下がったフェルミオン対生成(radiative return)。(3)Zポール及びWボゾン対生成の閾値での研究。これら全てにおいて、ビーム偏極(偏極度は電子80%、陽電子30~60%)を用いることでデータの増量と同じ効果が得られ、生成断面積の左右非対称性など多くの観測量を使うことにより、ヒッグス測定に関しては約2.5倍、Zポールの場合は約10倍に統計的感度が向上する。また、Zポールより上のエネルギーにおけるフェルミオン対生成においては、Zボゾンと光子の干渉が必ず起きるが、ビーム偏極を用いることで、このふたつの効果を分離することができ、フェルミオン粒子とZボゾン及び光子との結合定数について、右巻き粒子と左巻き粒子でそれぞれ独立に測定可能となる。大まかに言うと、ILC250の偏極・高輝度ビームで、標準理論の検証をこれまでより一桁以上良い精度で行うことができる。
ヒッグス測定を解釈する際に重要となる他の測定量として、荷電三点ゲージ結合(TGC)がある。これをもちいて標準理論を超える物理を探すこともできる。ILC250はLEPの100倍の精度でTGCを測定し、より高エネルギーのILC500においてはさらに2倍の精度で測定できる。この精度は、現在主流となっている標準理論を超える物理を検証するための有効場理論の枠組みにおいて、3つのTGCを同時に抽出する場合である。これに対し、LHCにおけるTGCの測定結果は、3つのTGCのうち、1つだけが標準理論の予言値からずれると仮定している。またILCでは、電子・陽電子のビーム偏極を用いて偏極ベクトルの向きを完全に決定でき、最も一般的な場合のTGCパラメータ28個を全て同時に決定することができる。
Zポールの物理
いわゆる電弱精密測定といえば、これまではZポールのことを指してきたが、ILC250においても、約9,000万個の可視Zボゾン事象がradiative returnを介して得られる。偏極ビームのおかげで、これらのデータを用いて左巻き電子と右巻き電子のZボゾンへの結合の非対称性(A_e)を現在の10倍以上の精度で直接測定することができ、Zボゾンと終状態フェルミオンの非対称性(A_f)を直接測定することができる。ビーム偏極無しの場合は、A_e・ A_fの積が決定できるのみであることと異なる。LEP/SLCと比較して、ILC250でのradiative returnのみでZポールにおける非対称性を約20分の1に改善することができる。現在、SLCとLEPの弱混合角の測定には3シグマの統計的な乖離があるが、これが標準理論を超える物理に起因するかどうかという長年の疑問にILCは決着をつけられるだろう。また、ILCは設計を少し変更すればZポールでの直接運転が可能となり、フェルミオン非対称性の精度はradiative returnを用いた場合からさらに約6~25倍に改善することができる。
Zポールよりも上のエネルギーでは、フェルミオン対生成が未知の重いZボゾン(いわゆるZ′ボゾン)の探索やフェルミオン四点結合、すなわち未知の相互作用が接触相互作用に対して良い感度がある。ILC250は6 TeVまでの質量を持つZ′ボゾンを間接的に発見することができ、ILC1000では18 TeVに至る。接触相互作用については、モデルの詳細に依存するが、ILC250では160 TeVまで、ILC1000では400 TeV付近までの複合性スケールを調べることができる。
新物理の直接探索
一見すると、ILC250における直接探索は、209GeVの衝突エネルギーを達成したLEPからわずかに改善されているだけのように見えるかもしれない。それにもかかわらず、ILCの非常に多いデータ量(LEPのWW閾値以上のデータの約2000倍)と、偏極ビーム、大幅に改善された検出器、そしてトリガーレス読み出しにより、多くの新しい標準理論を超える物理の探索が可能となる。例えば、Zボゾンと同時に生成される未知のスカラー粒子に対する感度については、ILC250はLEPと比べて1桁以上の改善ができる。また、LEPでは生成レートが低くデータが十分足りていなかったもう一つの例として、タウレプトンの超対称性パートナーであるタウ・スレプトンの探索がある。最も一般的なケースにおいては、26.3GeV以上のタウ・スレプトンは棄却されておらず、HL-LHCにおいても改善は期待できない。ILCの高精細検出器はビーム衝突軸に6mradまでせまる立体角までの検出能力を持ち、運動学的な限界値である衝突エネルギーの半分近くの質量まで探索する能力を持っている。実験的に最も困難とされているパラメータ領域についても探索が可能である。
LHCにおけるさらなる新粒子発見がないことで、暗黒物質粒子の質量が電弱スケールよりも下にあるフェルミオン型「Zポータル」模型に対する関心が強まってきている。例えば、未知のダークフォトンが標準理論の光子と混合することで検出が可能である。このような未知の現象の探索においては、Bファクトリー実験では到達できない10GeV以上で、かつ、LHC実験では制限を与えることができない150GeV以下の領域をILC250はカバーすることができる。
日本北部の北上山地で利用可能なトンネルの長さは50kmであるが、ILCのヒッグスファクトリーとしての段階では、その40%程度しか必要としない。将来、線形加速器を拡張し、電源と冷却設備を増強することで、現在の加速技術のままでも1 TeVの重心系エネルギーに到達するのに十分な長さである。ILC500へのアップグレードはILC250の約60%のコストがかかると想定される。また、1 TeVに到達するにはILC250の約100%のコストが必要であると想定される。これは、既に達成された加速勾配より少量の改善を仮定している (CERN Courier November/December 2020 p35)。これらの拡張計画により、ヒッグスファクトリーの次のステージとして、学術的な必要性や技術の進歩に応じた最適なエネルギーを提供することができる。
さらに高いエネルギーのILCについて
ILC500は500-600GeVの範囲のエネルギーを目標としており、ILC250と比較してヒッグス粒子結合の精度が概ね2倍、荷電三点ゲージ結合の精度は3~4倍向上できる。また、次の3つの重要な測定においても最適な感度を持つ。(1)トップクォーク電弱結合においては、様々な新物理の模型がZボゾンとの結合のずれを予言する(「モデルの感度」の図を参照)。(2)二重ヒッグス生成過程(e+-e → ZHH)により、ヒッグス自己結合の測定においては、ILC500ではヒッグス自己結合の精度は27%に達するのに対し、1 TeVではベクトルボゾン融合(VBF)過程を用いて10%の精度に達する。これらの数字は、ヒッグス自己結合が標準理論の予言値である場合を仮定しているが、一般的には、バリオジェネシス模型が要請するように、ヒッグス自己結合の値が大きい可能性もあり、その場合は精度はまったく状況が異なる。二重ヒッグス生成とVBFの双方の組み合わせにより、ヒッグス自己結合がどの値であっても10-20%の精度を保証することができる(「ヒッグス自己結合」の図を参照)。(3)トップクォーク湯川結合においては、ILC500で6.3%、550GeVで3.2%、1TeVで1.6%の測定精度と見積もられている。
ILC250では、生成レートが小さいことによりこれまで検出の限界があった様々な探索において、興味深い発見の可能性があるが、ILC500は運動学的にLEPを大きく超える範囲に到達可能である。例えば「自然さ」を標榜する超対称性模型においては、ヒッグス粒子の超対称性パートナー(ヒグシーノ粒子)は、Zボゾンやヒッグス粒子からそれほど離れていない質量を持っていなければならず、100〜300GeV程度と期待されている。ILC250ではこの範囲を開始することができ、より高いエネルギーのILCでは残りをカバーすることができる。HL-LHCにとっては困難を伴うヒグシーノ粒子群の間の質量が小さい場合においても、ILCではその崩壊を再構成することが可能である。
ILCは、現在、日本、米国、ヨーロッパの様々な国で政府レベルで議論されている唯一の将来加速器計画である。最も技術的に確立された提案でもあり、ILCの最先端の高周波空洞はすでに欧州XFELにおいて運用されている。欧州素粒子物理戦略2020年更新版において、日本でILCが前に進む場合には欧州の素粒子物理コミュニティは協働したいと述べている。最近では、ILC準備研究所の設立準備のためにILC国際推進チーム(IDT)が設置され、ILC建設開始に必要な技術的準備を全て行うことになっている。政府間交渉がうまくまとまれば、早ければ 2030 年代半ばにILCの試運転が開始されることとなる。
参考文献
P Bambade et al. 2019 arXiv:1903.01629.
K Fujii et al. 2020 arXiv:2007.03650.
K Fujii et al. 2019 arXiv:1908.11299.
著者
ドイツ電子シンクロトロン研究所(DESY) Jenny List
米国オレゴン大学 兼 パシフィックノースウェスト国立研究所(PNNL) Jan Strube
高エネルギー加速器研究機構(KEK) 田辺友彦