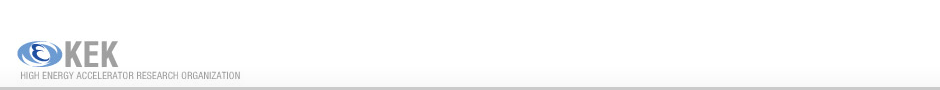
News@KEK
ATLAS実験グループが初の測定結果を公表
~ 高エネルギー物理学実験の論文を読む ~
2010年7月1日
スイス・ジュネーブにある欧州合同原子核研究機関(CERN)で始まったLHC加速器による陽子・陽子衝突実験から最初の物理結果が報告されました。LHC加速器では、現在4つの実験グループ、ALICE実験グループ、ATLAS実験グループ、CMS実験グループ、LHCb実験グループがデータを収集・解析を行っています。今回は日本から多くの研究者が参加しているATLAS実験グループの論文に焦点をあて最新の物理結果を報告します。
フィジックス・レター誌
ATLAS実験グループによるLHC加速器ビームを用いた最初の論文はオランダの出版会社エルゼビア(Elsevier)のフィジックス・レター(Physis Letters )誌のB688巻, 2010年(21ページから42ページ)に掲載されました。フィジックス・レターBは1967年来素粒子物理学や原子核物理学の実験結果や理論を掲載する老舗の物理専門学術誌です。レターとは結果の速報性を重視した比較的短い論文をさします。これに対して、レターでは論じきれなかった詳細な考察を加えた本論文も存在し、エルゼビア社ではニュークリア・フィジックスB(Nuclear Physics B)誌が本論文を掲載します。高エネルギー物理学の分野ではネイチャー(Nature)誌に投稿することは珍しく、専門学術誌に投稿するのが慣例です。
フィジックス・レターは商業誌なので、購入しなければ読むことはできません。専門学術誌の場合、掲載には審査が必要となるために、投稿から掲載までにある程度の時間が必要となります。レターも速報性がありますが、より速報性をあげるため、審査の前に、プレプリントという形で成果を先に配信することがあります。こちらは、WEBから無料で読むことができますので、紹介しておきます:
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1003/1003.3124v2.pdf (図1)
高エネルギー物理学実験の論文の構成
論文の構成は以下のようになっています。題名、アブストラクト(論文要約)のあと、
- 導入:目的とする物理とこれまでの背景、その重要性の議論(Introduction)
- ATLAS測定器の説明とその各部の性能について(The ATLAS detector)
- コンピュータシミュレーションによる反応の事前見積もり(Monte Carlo simulation)
- 衝突から生じる全反応からターゲットとなる反応を選別する条件(Event Selection)
- バックグランドとなる反応の寄与の見積もり(Background contribution)
- 反応選択の効率の見積もり(Selection efficiency)
- 理論と比較できる形にデータを補正する手法(Correction procedure)
- 系統誤差の解析(Systematic uncertainties)
- 実験の結果(Results)
- 結論(Conclusion)
続いて謝辞が述べられ、参考文献のリストへと続きます。今回の論文はここまでで、23ページです。通常は、題名のすぐ下に執筆著者リストがつけられるのですが、ATLAS実験グループの場合、著者数が約3200名になるために、参考文献リストのあと、24ページから40ページが著者リストにあてられています。
この章立ては高エネルギー実験の解析論文では典型的な形になっていますので、このパターンに慣れれば、いろいろな論文が読めるようになります。
発生した荷電粒子数の初めての測定
この論文では、昨年の12月に取得した衝突のエネルギーが900GeV(GeV=10億電子ボルト)のデータから、陽子と陽子が衝突したときに生じた反応中の電気を帯びた粒子(荷電粒子)数の測定結果が論じられています(図2)。
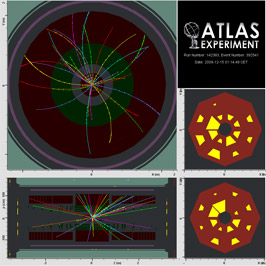
図2
画像提供:CERN アトラス実験グループ
この論文の解析に用いられた900GeVにおけるソフトな散乱の例。図中の一点(衝突点)から放射状に出ている線が、散乱によって生じた荷電粒子の飛跡を表す。線上の点は荷電粒子が検出器上に残した信号。左上はビーム軸に沿って検出器を見た図(中心がビーム軸)、左下は検出器をビームに垂直な方向から見たもの。右の2つの図は左下の図の両端の位置においてある検出器で、生じた粒子のうちビーム方向の近くのものをとらえるために置かれている。黄色の台形は検出器中に落とされたエネルギーで、粒子の数におおむね比例する。
陽子は素粒子ではなく、クォークやグルーオンといった素粒子がいっぱい詰まっている複合粒子です。陽子同士をぶつけると、その中のクォークやグルーオンが正面衝突に近い激しい散乱を起こすことがあります。その高エネルギー状態から未知の粒子を作り出すのがLHC実験の原理です。しかし、ほとんどの場合には、このような激しい散乱にはなりません。多数のボールを同時に投げ合ったときのように、陽子の中身の多数のクォークやグルーオンが複雑にぶつかり合うのですが、ひとつひとつの衝突を見てみると、正面衝突に近い散乱はめったに起こらず、粒子の多くはほとんど散乱せずにすり抜けてしまいます。このような散乱現象を、激しい(ハードな)散乱と区別してソフトな散乱と呼んでいます。
このような散乱は、新現象の発見には役立ちません。ではなぜこのような測定を行ったのでしょうか。それは、こうした散乱が、重要な激しい散乱と同時に起きるからなのです。陽子の中で激しい散乱に関与しなかった残りのクォークやグルーオンは、裏でソフトな散乱を起こします。そこから生成した粒子は、激しい散乱からの粒子と重なり、測定のじゃまをすることがあります。その効果を補正するためには、このような散乱からの粒子の生成を細かく知る必要があるのです。
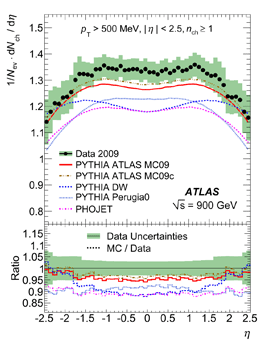
図3
ATLAS測定器による荷電粒子数の分布を、η(本文参照)で表したもの。黒丸は測定点、緑の範囲は測定の誤差を表す。曲線はいろいろな予想曲線。下の図の縦軸は各理論予測の粒子数を測定結果で割ったもの。
(arXiv:1003.3124v2より)
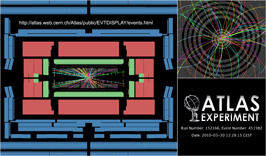
図4
画像提供:CERN アトラス実験グループ
7000GeV の初衝突の事象の一つ。衝突エネルギーが高くなり、生成された粒子数も多くなっている。
今回の論文では、1つ以上の荷電粒子が作られた衝突事象をとらえ、生成した粒子の数、生成した粒子の角度分布などから、散乱のほとんどを占めるソフトな散乱の性質を調べました。この論文は初の実験データということで、レターとしては比較的詳しくデータ解析の方法が述べられています。
こうして得られた荷電粒子の数を示したのが、図3です。横軸は擬ラピディティ(η)と呼ばれる量です。陽子が飛んでくる軸に対しての荷電粒子が散乱する角度に対応する変数で、η=2.5は約10度にη=0は90度にη=-2.5は約170度に対応します。縦軸は、選別された全反応中、ηに対応した方向に飛んで行った荷電粒子の総数を全反応総数で割ったもので、その角度に飛んだ平均の荷電粒子の数を表します。黒点がデータ、その周辺の緑の領域は測定誤差を示します。粒子はηに対してほぼ一様に生成されていることがわかります。
一方、いろいろな色の点線は理論から予測される分布曲線です。この図から、理論はおおむね実験を再現していますが、データに比べ若干理論が予言する粒子の数が少なめであり、またモデルによりかなりばらつきがあることがわかります。この論文が対象とするソフトな散乱は、多数の粒子がからみ合うことから理論的な計算が難しく、今のところ過去の様々な実験データに合うように定式化を行い、モデルを組み立てています。各々のモデルの予測は、その際に用いるデータや定式化の方法により変わってきます。ここで用いられた理論の中には、この測定の対象である事象と異なる散乱事象を用いてモデルの改良を行ったものもあります。よって、モデルには比較する測定データの種類によって得手・不得手があり得ます。それがこの比較であらわになったと言えるでしょう。現在、LHC実験では衝突エネルギーが7000GeVでデータを収集しています(図4)。異なる衝突エネルギーからのデータを用いることで、モデルをさらに改良することができます。今後の解析が待たれるところです。
