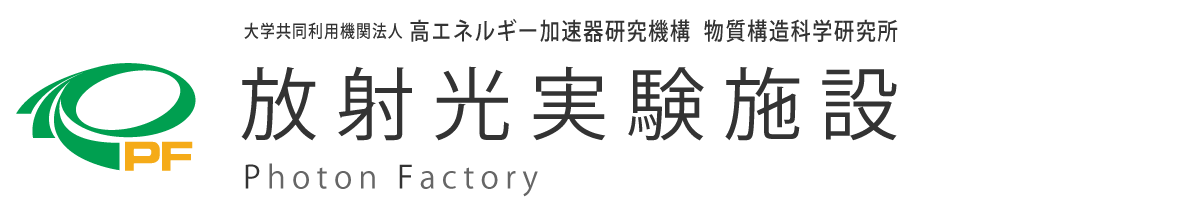2025S2-001 X線顕微鏡の多次元ビッグデータからの革新的情報抽出
| 実験責任者 | 所属 | ステーション | 期 間 |
|---|---|---|---|
| 木村 正雄 | KEK-IMSS-PF | AR-NW2A, 19A/B, 15A1, 9A, 9C, 12C, AR-NW10A | 2025/04〜2028/03 |
| 近年のX線顕微鏡の技術発展は著しく、マルチスケール&マルチモーダルの多次元データが比較的容易に得られる様になった。得られる多次元データは、データサイズそのものが膨大であるだけでなく、データに様々かつ膨大な情報が内在されているという両方の意味でまさにビッグデータである。そのために、目的に沿った情報を引き出すためには、人間による手作業だけでは限界がある。 我々は、今まで、各種X線顕微分光法の設備導入と計測技術確立(2019S2-002)、計測された顕微鏡データとシミュレーション等の計算科学手法のデジタルツイン解析(2022S2-001)を進めてきた。そしてビッグデータからの情報抽出には数理科学および情報科学を用いたアプローチが非常に有用であることを示してきた。そこで、本課題では、特に今後の発展が期待できる「パーシステントホモロジーによる位相的データ解析(Topological data analysis; TDA)」にターゲットを絞り、数理科学を活用してX線顕微法のビッグデータに潜む情報を抽出するための方法論を確立することを目標とする。具体的には、材料科学や地球科学の重要課題を取り上げ、多次元空間での(広義の)‘かたち’と‘うごき’に注目することで情報を引き出す。 そのため、本課題では、構造材料のき裂、二次電池の伝導/拡散パス、海洋プレートでの水素発生、という、対象とする現象やその空間スケールが全く違う3つの系をとりあげ多次元空間での(広義の)‘かたち’と‘うごき’に注目することで情報を抽出する。さらにその情報とマクロ特性の相関を情報科学的に解明し、反応起点(trigger site)の予測につなげる。 取り組む3つの系は、必要となるX線顕微法の基本的な装置環境が既に整っている。さらに、我々が分担者として参画する国プロ(未来社会創造事業、学術変革領域研究)で研究展開しており、材料開発研究や数理研究等の多くの関係者との共同研究体制が整っている。これにより、3年間という限られた期間内でも迅速にインパクトある成果の創出が期待できる。 |
関連課題 | ||
成果
- 論文等(KEK放射光共同利用実験研究成果データベースの画面が別タブで開きます)
PF Activity Report
プレスリリース・関連記事