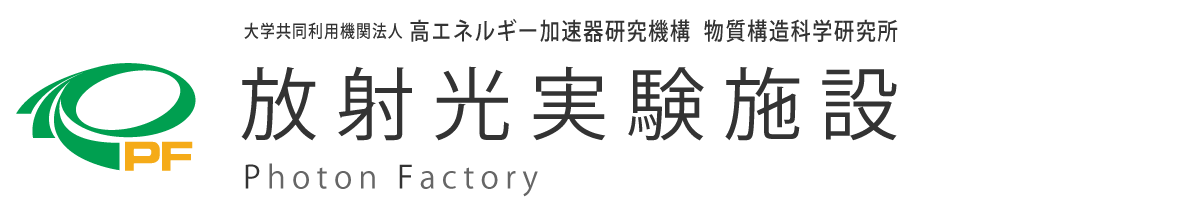共同利用実験課題申請
更新日:2025年5月9日
高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所の放射光実験施設(フォトンファクトリー)は、電子蓄積リングから放出される放射光を用いて学術研究を行うための全国共同利用研究施設です。下記の要領で共同利用実験課題(成果公開の学術研究に限る) を公募します。また、低速陽電子実験施設の共同利用実験課題も併せて公募します(課題審査等は放射光共同利用に準じて実施します)。
課題募集状況
以下の課題の応募を受付けています。課題の詳細は、下記「放射光共同利用実験課題公募要項」を参照してください。
| 申請区分 | 申請期間 |
|---|---|
| G型(一般)、T型(大学院生奨励)、S2型(特別2) RD型(開発研究) |
次の課題公募は、2025年10月上旬開始を予定しています。 ※採択された課題は、2026年4月1日から有効です。 |
| P型(初心者)、U型(緊急かつ重要)、S1型(特別1) | 随時募集 |
放射光共同利用実験課題公募要項
最近の変更点
- (2025年度後期課題公募からの変更)
- (RD型課題の募集開始について)RD型課題 (BL-11を用いたマルチビーム利用および通常のビームラインでは実施が難しい放射光関連技術の開発研究のための課題区分) の募集が開始されました。 申請資格・申請前の打ち合わせ等、他の課題区分と申請方法が大きく異なります。詳細はRD型課題の説明を参照してください。
- (2024年度後期課題公募からの変更)
- (「結晶準備状況」の提出必須化について)第4分科ビームライン(BL-1A, 5A, 17A, AR-NE3A, NW12A)を利用する全ての課題で、課題申請時に「結晶準備状況」の提出が必須になりました。提出されない場合、課題は不採択になります。書式は2024年度後期課題公募から新しくなっています。詳細は、第4分科への申請についてを参照してください。
- (2023年度前期課題公募からの変更)
- (学生のG型申請について)一定の条件の下、大学院生もG型課題に申請可能となりました。詳細はG型課題の説明を参照してください。
申請資格
- 実験責任者(課題責任者)
- 国内外の大学および公的研究機関の教員・研究員・技術職員、成果公開型の学術研究を認める民間企業の研究者、又はこれらと同等と所長が認める者。
- 国内の大学に所属する大学院生(博士後期課程)(T型・G型)。
- 日本語を解さない実験責任者の申請では、日本に在住し日本語を解する研究者 (Contact Person in Japan: CPJ)が必要になります。
- 課題申請区分ごとの申請資格の詳細については、申請区分を参照してください。
- 実験責任者および実験参加者
- 放射線業務従事者登録が可能であること。
- 賠償責任保険および損害保険に加入していること。
申請区分
- 申請区分は以下の通りです。申請区分ごとに、課題の性格、申請資格、採択後の手続き等が大きく異なります。詳細については、"PF共同利用実験課題:申請区分"を参照してください。 PF共同利用実験課題:申請区分
| 申請区分 | 課題の概要 | 課題の有効期間 | 募集時期 |
|---|---|---|---|
| G型(一般) | 一般的な放射光利用実験 | 2年間 | 年2回:例年5月・11月締切 |
| S2型(特別2) | 長期のビームタイムを必要とする放射光を駆使した高度な研究。技術的困難度が高いが成功すれば高い評価の得られる実験も含む | 3年間 | 年2回:例年5月・11月締切 |
| T型(大学院生奨励) | PFを高度に活用した優れた研究を主体的に推進する大学院生(博士課程)を、大学とPFが共同して指導、支援を行い、放射光科学の将来を担う人材の育成を行う | 3年間 | 年2回:例年5月・11月締切 | RD型(開発研究) | 開発研究多機能ビームライン(BL-11)を利用する実験(マルチビーム利用および通常のビームラインでは実施が難しい放射光関連技術の開発研究) | 3年間 | 年2回:例年5月・11月締切 |
| P型(初心者) | 放射光を利用した当該実験手法の未経験者による実験 | 1年間 | 随時 |
| S1型(特別1) | ビームライン改造・建設および大型装置の整備を伴うプロジェクト研究 | 3~5年間 | 随時 |
| U型(緊急かつ重要) | 次回の審査委員会を待てないほど緊急で、かつ採択済みの課題に優先して実施する価値のある極めて重要な課題。なお、対応可能な場合は、採択済みの課題に優先するほどではないが、緊急性・重要性の高い申請についても受け付ける | - | 随時 |
実験ステーション
- 利用できる実験ステーション(ビームライン)・実験装置について
- 放射光実験施設のPF、PF-ARの実験ステーション、および低速陽電子実験施設の実験ステーション。 ビームライン・実験ステーション
- PFでは、ビームラインを測定手法グループとしてまとめ、それらを束ねた6つのビームライン群に分類して運用しています。審査においては、利用希望のビームライン群に対応した審査分科が割り当てられます。ビームラインと審査分科の対応は以下を参照してください。
ビームライン群と実験課題審査分科
課題申請および審査
- 申請書の作成について
共同利用実験課題申請にあたって注意頂きたいことについて、課題申請書の作成についてにまとめています。内容を十分に理解して申請書を作成してください。申請方法および実験に関して不明な点がある場合には、十分に余裕を持って早めの問合せをお願いします。 課題申請書の作成について - 申請について
共同利用実験課題申請書の作成および提出は、KEK実験課題申請システムより行ないます。申請書作成・申請手順・操作等については、システム上のマニュアルや注意書きに従ってください。※S1型およびRD型は申請方法が異なります。詳細は各申請区分の説明をご参照ください。
KEK実験課題申請システム
- 申請時の注意点
-
複数の分科にまたがる課題申請について
- 選択した実験ステーションによって審査分科が一義的に割り当てられます。異なる審査分科に属する複数の実験ステーションを選択した場合は、複数の審査分科が割り当てられます。したがって、申請書にはそれぞれのビームライン(審査分科・実験手法)ごとの詳細な記述が求められます。
実験ステーションと審査分科との対応は、ビームライン群と実験課題審査分科を参照してください。
(例)一連の研究を遂行するために、異なる実験手法(X線構造解析とX線吸収分光など)を用いる場合で、一件の課題申請書にて申請をする場合は、それぞれの手法に関して詳細を記述してください。
- 選択した実験ステーションによって審査分科が一義的に割り当てられます。異なる審査分科に属する複数の実験ステーションを選択した場合は、複数の審査分科が割り当てられます。したがって、申請書にはそれぞれのビームライン(審査分科・実験手法)ごとの詳細な記述が求められます。
- (過去の成果について)これまでに放射光共同利用実験課題が採択され、実験をしたことがある方の申請については、過去の課題に関する論文登録状況も審査担当者から参照されます。あらかじめ、KEK成果管理システム)への論文の登録状況を確認してから申請を行ってください。論文登録状況が放射光共同利用実験審査委員会(PF-PAC)で定められた評価の基準を満たさない場合は、論文の登録もしくは、論文が出版できていない理由書の提出がないと課題申請をすることができません。
- 課題の審査
- 申請された実験課題申請書は、物質構造科学研究所に設置されたPF-PACで審査し、物質構造科学研究所運営会議の議を経て、所長が採否の決定をします。緊急かつ重要な実験課題(U型)、初心者実験(P型)については、申請書受理後直ちに審査を行い、その都度採否を決定します。
- 課題審査では学問および技術的な価値、および実験可能性に着目して課題の評価が行われます。審査手続きと評価の基準については、放射光共同利用実験課題審査手続き・評価基準を参照してください。
- 審査にあたって、PF-PACは必要に応じて実験責任者に追加の説明を求めることがあります。
- 審査結果については、実験責任者およびContact Person in Japanにお知らせします。
- ビームタイム配分
- 採択された課題の内、原則として評点の高い課題から順にビームタイムが配分されます。したがって、課題が採択されたことは必ずしも申請されたビームタイムの配分を保障するものではありません。
- ビームタイムの配分は年3回の運転期ごとに行われますので、使用するビームラインの担当者と連絡をとってください。
- 実験成果の公表
本共同利用実験は成果公開型であり、研究成果は、学術誌への投稿・学会発表等を通じた公表が求められます。
実験成果を発表する際には、機構における研究であることを明記するとともに、出版後に当該論文等をKEK成果管理システムに登録してください。PF Activity Report(PFACR)には、原則として一課題につき少なくとも一報のユーザーレポート提出をお願いします。実験を実施できなかったなどの理由でPFACRを提出できない場合には実験終了届を提出してください。
その他注意事項
- (平和利用)共同利用実験は、平和目的に限ることとし、その判断は日本物理学会第33回臨時総会の決議3およびその具体的取り扱いを定めた第522回委員会議決定に準拠するものとします。
- (資格の追記事項)経済産業省が公表している外国ユーザーリスト(End user list)に掲載されている機関に所属する応募者およびNPT未加盟国の応募者については、文部科学省と協議し資格の有無を決定します。
- (知的財産権の帰属)本共同利用実験により得られた知的財産権の帰属については、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構知的財産取扱規程に基づき、その都度協議することになります。
- (個人情報の取扱い)応募により提供された個人情報は、課題審査および課題採択後に共同利用実験を円滑に実施するための連絡等の目的で利用いたします。また、採択課題については、本機構のウェブページおよび刊行物に実験責任者氏名・所属および実験課題名等を掲載することをご了承ください。
- (課題採択後の手続き)課題採択後の手続きの詳細は、来所・実験の手続きを参照してください。
- (旅費の支援)国内の大学等からの利用に当たり、PFのルールに基づき旅費、滞在費のサポートを行います。また、宿舎等は空きのある範囲で利用可能です。
問合せ先
- 申請に関すること
- 高エネルギー加速器研究機構 研究協力部 共同利用支援課 共同利用係
- E-mail: kyodo1[at]mail.kek.jp
- TEL :029(864)5126
- 実験に関すること
- 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 放射光実験施設
- E-mail: pfexconsult[at]pfiqst.kek.jp