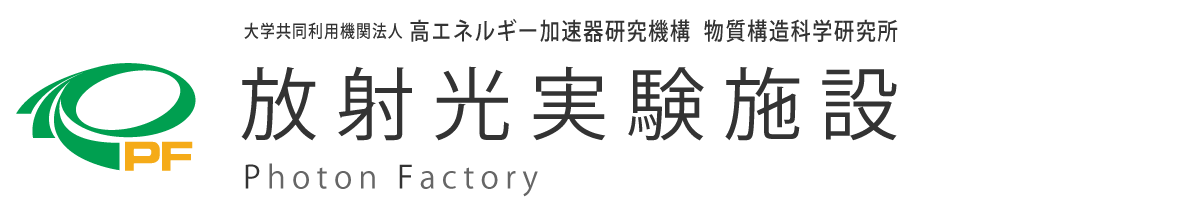課題申請書の作成について
更新日:2025年9月29日
- 共同利用実験課題申請書の作成および提出は、KEK実験課題申請システムより行ないます(RD型を除く)。
- このページには、課題申請書を作成する際の注意点についてまとめています。
- 2025年10月から、申請書の様式が変更されました。変更点に十分注意して申請書を作成してください。特に、項目III(研究意義)およびIV(実験方法)については、テンプレートを使用して作成したPDFのアップロードに限定されました。
- 課題の募集については、「放射光共同利用実験課題公募要項」を参照してください。
申請書全般の注意点
実験責任者 基本情報(実験課題名) I.ビームタイム II.研究グループメンバー
詳細情報(項目 III~VII): III.研究意義 研究分野キーワード IV.実験方法 実験手法キーワード V. 安全 VI.成果 VII.外部資金 課題区分による追加項目
申請書全般の注意点
- 審査は申請書に記述された内容について行ないますので、具体的に記述してください。
- 課題の審査の流れや評価基準については、放射光共同利用実験課題審査手続き・評価基準を参照してください。
- 申請書を提出する前に、申請システムで作成されるPDFの内容を十分に確認してください。レフェリーは申請書のPDFファイルを読んで評価します。誤字脱字の他、文字化け・文字数オーバーに十分注意してください。
特に注意頂きたい事項
複数の分科にまたがる課題申請について
- 選択した実験ステーションによって審査分科が一義的に決まります。異なる審査分科に属する複数の実験ステーションを選択した場合は、複数の審査分科が割り当てられます。したがって、申請書にはそれぞれのビームライン(審査分科・実験手法)ごとの詳細な記述が求められます。
実験ステーションと審査分科との対応は、ビームライン群と実験課題審査分科を参照してください。
(例)一連の研究を遂行するために、異なる実験手法(X線構造解析とX線吸収分光など)を用いる場合で、一件の課題申請書にて申請をする場合は、それぞれの手法に関して詳細を記述してください。
第4分科への申請について(BL-1A, 5A, 17A, AR-NE3A, NW12Aを利用する申請)
- 第4分科のビームラインを利用したX線構造解析実験を予定している場合は、課題申請時に「結晶準備状況一覧」を必ずアップロードしてください。下記リンクもしくは、実験課題申請システムからダウンロードできます。 結晶準備状況一覧
- 第4分科のビームラインでは、凍結結晶に限り遺伝子組換え体のサンプルの持ち込み(封じ込めレベル1のものに限る)が可能です。これにより、バキュロウイルスの混入の可能性が排除できない結晶の測定が可能になります。該当試料を持ち込む予定がある場合は、申請書 V. 実験の安全性の欄に必ずその詳細情報を記載してください。
- 選択した実験ステーションによって審査分科が一義的に決まります。異なる審査分科に属する複数の実験ステーションを選択した場合は、複数の審査分科が割り当てられます。したがって、申請書にはそれぞれのビームライン(審査分科・実験手法)ごとの詳細な記述が求められます。
各項目の注意事項
実験責任者
- 「新規申請」ボタンをクリックすると、ログインした方の氏名、Eメール、所属等(共同利用者支援システムに登録された情報です)がデフォルトで実験責任者欄に入力されます。これまでに複数の所属・職名等を登録された方は全て表示されますので、正しいものを選択してください。
- 所属等の情報に変更がある場合、情報が正しくない場合は、共同利用者支援システムで情報を修正してから、申請書を作成してください。
- 日本語を解さない実験責任者の場合には、日本に在住し日本語を解する研究者Contact Person in Japan (CPJ)が必要になります。主な役割は以下のとおりです。
- KEKと実験責任者間の連絡
- 来日のための便宜供与またはそのための連絡
- 実験支援または適当な支援者の斡旋
基本情報(実験課題名)
- 「実験課題名」は、研究内容を具体的に表わす簡単なものとし、包括的にならないよう注意してください(成果公表時の報文名をイメージしてください)。
I. 希望ビームタイム
- 各ステーション、希望時期ごとに、時間または日単位で記入してください。
- この項目で選択していないステーションは、実験に利用できませんので注意してください。
II. 研究グループメンバー
- 申請に関わる研究グループメンバー全体を記入してください。放射光実験に直接参加しない人(試料提供等)についても記入してください。
- "研究グループでの役割"の欄が追加されました。研究を進めていく上での各人の役割を具体的に記入してください(例:放射光実験、試料調製、データ解析、など)
- 必ず本人の了承を得た上で記入してください。特に、PFの実験ステーション担当者の名前を無断で記入しないでください。
- (学部学生の実験参加)学部学生を実験参加者に記載することはできませんが、 課題が採択され有効となる時点での大学院進学を予定している学部学生については、 実験参加者としてリストに記載することが可能です。 この場合、申請書の職名欄に、申請時の学年とともに 「○○年○○月 大学院進学予定」である旨記入してください。
詳細情報(項目 III~VII)(各項目の字数制限に注意してください)
III. 研究の意義、目的、特色、期待される成果(PFを必要とする理由も含む)
- テンプレート(下記リンクもしくは、実験課題申請システムからダウンロードできます)を使用して作成し、PDFファイル形式でアップロードしてください。
- 図や表などを含めることができます。図や表を含めてPDFで最大2ページで記述してください(S2型課題については項目IIIと項目IVは、合計で最大10ページ程度で記述してください)。PDFファイルのサイズは5MB以下にしてください。
- 複数分科・手法の課題については、各分科・手法の審査が問題無く行えるように、各手法について詳細に記述してください。
- T型課題の場合は、大学院での研究計画と本申請での実験内容の関連についても記載してください。
- 研究の背景などを説明するための引用文献等は、項目IIIもしくは IVに記述してください。(VIには研究グループによる成果・論文のみを記してください)
研究分野キーワード
- プルダウンメニューから申請課題の研究分野を選択してください(4つまで)。メニューにないキーワードを入力するには、「その他」を選択して、横のテキストボックスに直接入力してください。
IV. 実験の方法、ステーション選定の理由、ビームタイム算出の根拠、および本申請に関わる試料・装置の準備状況
- テンプレート(下記リンクもしくは、実験課題申請システムからダウンロードできます)を使用して作成し、PDFファイル形式でアップロードしてください。
- 図や表などを含めることができます。図や表を含めてPDFで最大2ページで記述してください(S2型課題については項目IIIと項目IVは、合計で最大10ページ程度で記述してください)。PDFファイルのサイズは5MB以下にしてください。
- 複数分科・手法の課題については、各分科・手法の審査が問題無く行えるように、各手法について詳細に記述してください。
- 研究の背景などを説明するための引用文献等は、項目IIIもしくは IVに記述してください。(VIには研究グループによる成果・論文のみを記してください)
- 実験の実施可能性を説明するために、試料の準備状況、予備実験の状況などについて記述する必要がある場合には、項目IVに記入してください。
- 標準的なセットアップ以外での実験の場合は、必要とする装置・器具、レイアウトについて詳細を記述してください。必要に応じて、実験に必要な「施設にある装置、器具」および「持ち込む装置、器具」についてそれぞれ記述してください。
- ステーション選定の理由が判断できるように、必要に応じて実験に必要とする光の性能(エネルギー、強度、ビームサイズ等)を記述してください。
- 実験の安全性の確保に関する説明は、項目Vにまとめて記述してください。
実験手法キーワード
- プルダウンメニューから申請課題の実験手法を選択してください(3つまで)。メニューにないキーワードを入力するには、「その他」を選択して、横のテキストボックスに直接入力してください。
V. 実験の安全性に対する記述、対策 (化学、生物、放射線、高電圧、高圧ガス、真空汚染等)
- 実験の安全性の確保に関する説明について
- 有害な物質については、その利用法、除害法、保管方法等を記入してください。
- 特に有害性の大きい試料(可燃性または有毒なガス、放射性同位元素、核燃料物質)については、申請前にステーション担当者または当該安全担当者に相談のうえ、安全対策を記入してください。
- 試料以外でも安全に係わること(危険物、高温、高圧ガス、高電圧等)および超高真空を汚染するおそれのある場合は、その対策を明記してください。
- 生物試料を用いる場合の注意点。以下の事項を項目Vに必ず記入してください ※生物安全に関する事項の記述不足により、採択が条件付き(留保)となる事例が多発しています。十分に注意して記述してください。
- 各試料について、由来生物種、病原性、感染性、毒性について記入してください。
- 試料が遺伝子組換え体を用いて調製された場合は、由来生物種に加えて、どのような発現系を用いたかについて記述してください。遺伝子組換え体を含む可能性のある試料の持ち込みは、第4分科のビームラインに限定されます。
- 動物個体および動物・ヒト由来の試料の利用については、所属機関の倫理委員会等の承認が必要です。承認が得られていることを申請書に明記してください。承認手続き中の場合でも課題申請は可能ですが、承認が得られるまで課題の採択は保留されます。
- 生物試料の利用について不明な点がある場合は、申請前にご相談ください。
- "試料一覧"の提出について(必須)
- 実験で持ち込む予定の試料・薬品等について、試料・薬品名、形態、数量、使用目的および性質をまとめた一覧の提出が必要です。入力用ファイルに記入し、PDFに変換して課題申請システムから提出してください。 試料一覧入力ファイル
VI. 本申請に関わる研究グループの成果・論文
- 項目VIには、課題を申請する研究グループによる成果・論文のみを記入してください。研究の背景や実験方法などを説明するために文献等を参照する場合は、項目IIIもしくはIVに引用であることを明確にして記述してください。
- 記入する成果・論文等は、申請内容(実験内容)に直接関係するものに限定されます。過去の年数については限定されません。
- 文献名やDOIなどを使うなど、レフェリーが直接参照できるような形式で入力してください。文献の内容が分かるように、必ずタイトルを入力してください。
(例えば、以下のような形式で) ○ Harada, K., et al,. "Conceptual design of the Hybrid Ring with superconducting linac", Journal of Synchrotron Radiation, 29, 118-24 (2022).DOI:10.1107/S1600577521012753 - ※注意:試料の準備状況や、予備実験の状況などについて記述する必要がある場合は、項目IVに記してください。
VII. 外部資金獲得状況
- 課題申請した研究に関係する外部資金の獲得状況を記述してください。
課題区分による追加項目
- U型課題:「緊急かつ重要である理由の説明、前回申請できなかった理由」について記述する箇所があります。課題の緊急性・重要性について説明してください。
- P型課題:申請を行う前にステーション担当者との事前打ち合わせが必要です。「ステーション担当者との打ち合わせが済んでいるか」の確認、打合せを行った担当者名を記述してください。
- T型課題:申請を行う前に大学側教員、PF側指導教員と十分な事前打ち合わせが必要です。「大学側指導教員、PF側指導教員との打ち合わせが済んでいるか」の確認、「PF側指導教員名」および「博士課程修了予定年月日」について記述する箇所があります。
- S2型課題:項目III(研究意義)と項目IV(実験方法)は、合計で最大10ページ程度で記述してください。「S2型課題を必要とする理由、長いビームタイムを必要とする理由、マンパワーの目処、特別運転を必要とする場合はその仕様(準定常的な運転モードを除く)と理由、購入を希望する物品リスト(品名、型名、価格、納期、用途)」と「研究概要」について記述する箇所があります。
- RD課題:専用の申請書テンプレート を使用して申請書を作成し、メール添付の形式で提出して申請します。 詳細はRD型課題の説明を参照してください。「申請書テンプレート内の注記」および「RD型課題の説明」とこのページの説明が異なる箇所については、申請書内の注記および課題区分の説明の内容を優先してください。