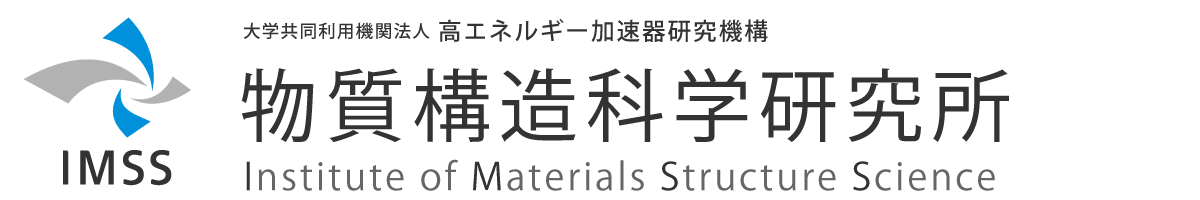国際協力
基礎科学はもともと国境のない学問ですが、特に研究施設の高度化と大型化が進むにつれ、国を越えた交流がますます重要になっています。物構研が所属する高エネルギー加速器研究機構(KEK)は、国際共同利用研究の場を提供し、世界的な役割分担を拡充し続けています。一方、海外協力研究は、我が国での研究を補う役目を果たしています。特に、本機構は日本側の代表機関として、高エネルギー物理学での日米協力、日欧協力及び中性子散乱研究のための日英協力を推進しています。
 下村理物構研所長(2011年当時、左)とAndrew Taylar ISIS施設長
下村理物構研所長(2011年当時、左)とAndrew Taylar ISIS施設長
放射光施設の国際協力
フォトンファクトリーでは1992年よりオーストラリアビームラインが稼働し、オーストラリア研究者による第一級の研究成果の創出だけでなく、研究技術や人材育成によりオーストラリアの放射光施設Australian Synchrotronの設立に寄与しました。また、2009年にはインドビームラインが設置され、インド側ユーザーによる構造解析の基礎研究の展開とともにインドの若手研究者育成のため、2011年より実験を開始しています。
近年では、アジア・オセアニア地域の放射光連携に力を入れており、中東地域のSESAME加速器の建設、研究者の養成に協力しています。
 PFに設置されたインドビームライン、BL-18B
PFに設置されたインドビームライン、BL-18B
中性子・ミュオン実験施設の国際協力
1986年から続く日英協定では、英国ISISのMARIチョッパー分光器の建設や、研究者の長期派遣などの研究協力を行ってきました。これが我が国の中性子科学の発展と、J-PARCの中性子分光器群建設に繋がりました。
また、スイスPSI、カナダTRIUMF研究所などともミュオンビームの高度利用実験、実験装置・解析技術の開発による研究者相互の交流を行い、国際協力のもと、基礎研究に取り組んでいます。