文化財と最先端科学、そして伝統技術の「いま」を知る特別講演会を開催します。 放射光や中性子・ミュオンビームを用いた“触れずに分析する”文化財研究、キプロスを舞台とした非破壊調査、そしてNHK大河ドラマでも注目される浮世絵の伝統木版技術の継承など、理系と文系の枠を越えた視点から、文化と科学のつながりをひもときます。
科学や歴史に興味のある方、どなたでもご参加いただけます。ぜひご来場ください。
文化財に触れずにビームを使って分析する
国際基督教大学 久保 謙哉 特任教授
専門:ミュオン科学
貴重な資料を分析するときに、傷をつけたり外観を変えてしまうことはできません。放射光と呼ばれる強力な光や、中性子ビームやミュオンビームを使うと、資料の表面から内部まで、資料に触れることなく使われている材料や素材の性質を調べることができます。どのような仕組みでそのようなことが可能なのか、科学的な原理を平易に解説し応用例を紹介します。
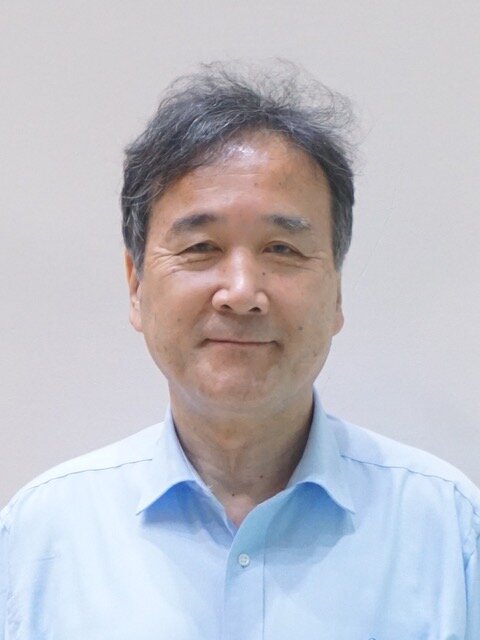
【同時通訳】ミュオン科学の文化遺産と考古学への応用における進展、課題、および可能性——特に人類生物考古学に焦点を当てて
キプロス研究所 キルシ O. ローレンツ 准教授
専門:人類生物考古学;先端科学技術応用
過去から現代に至るまで残されてきた遺物を研究する際、私たち専門家はもちろん、人類全体も、他分野で開発された最先端の技術や科学的アプローチを応用することで大きな恩恵を受けています。こうした最前線の探究には、学際的・超学際的な連携が不可欠です。ミュオンX線の文化財科学や考古学への応用も、その好例といえるでしょう。 本講演では、ミュオン科学を文化財や考古学、特に人骨考古学に応用する上での進展、課題、そして今後の可能性について考察します。これまでに達成された成果をふり返り、応用現場の視点から見た課題を整理したうえで、ミュオンX線や計測技術の専門家と、文化財研究者および(生物)考古学者との間の新たな学際研究のあり方と、その展望を探ります。

世界に誇る日本の浮世絵、その制作技術の現在
公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団 中山 周 理事
2025年は、歌麿や写楽を生み出した版元・蔦屋重三郎を描くNHK大河ドラマ「べらぼう」が話題を呼び、浮世絵への関心が改めて高まっています。
本講演では、その歴史的背景や芸術的価値に触れながら、制作を支える伝統木版技術の“現在”に焦点を当てます。絵師・彫師・摺師による分業で成り立つ浮世絵の制作技術は、職人の高齢化や後継者不足により継承の危機に直面しています。こうした中で技術の保存と次世代への伝承に取り組む財団の活動を通して、伝統的な木版技術が現代にどのように受け継がれているのかをご紹介します。

| 13:30〜13:35 | ご挨拶 | |
|---|---|---|
| 13:35〜14:15 | 文化財に触れずにビームを使って分析する | 久保 謙哉 特任教授(国際基督教大学) |
| 14:15〜14:25 | 休憩 | |
| 14:25〜15:05 | 【同時通訳】ミュオン科学の文化遺産と考古学への応用における進展、課題、および可能性——特に人類生物考古学に焦点を当てて | キルシ O. ローレンツ 准教授(キプロス研究所) |
| 15:05〜15:15 | 休憩 | |
| 15:15〜15:55 | 世界に誇る日本の浮世絵、その制作技術の現在 | 中山 周 理事(公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団) |
| 15:55〜16:00 | アンケートへのご回答 | |
お申込みには、Peatix への会員登録が必要です。
▶ 文理融合シンポジウム一般講演会参加申込み
お申込みフォームにご記入いただいた個人情報は、本プログラムに関する目的以外での利用や、第三者への開示はいたしません。ご入力いただいた情報は、以下のご案内に使用させていただきます。
この一般講演会は、放射光・中性子・ミュオンなどの量子ビームを利用する文化財研究の第一人者が一堂に会して、これまでの考古学研究、並びに関連研究、更に分析技術を紹介し、文理融合研究の可能性を探る文理融合シンポジウムのプログラムの一部として開催されます。
第10回 文理融合シンポジウム 量子ビームで歴史を探る ー加速器が紡ぐ文理融合の地平ー
文理融合シンポジウム 世話人
メール:bunri_yugo[at]ml.post.kek.jp
[at]を「@」に置き換えてください。