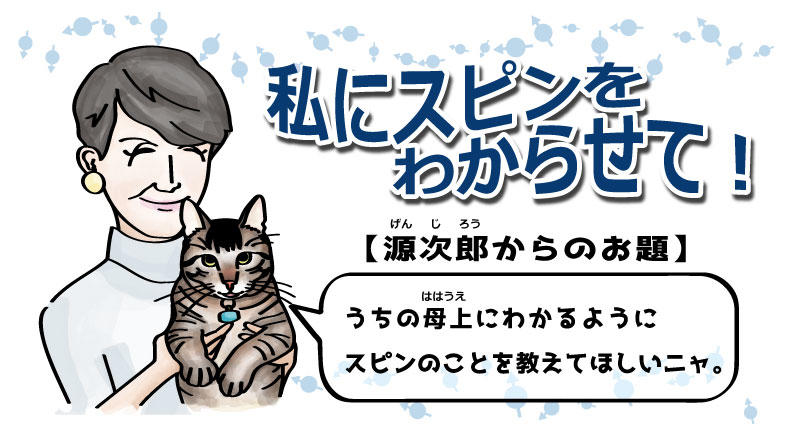
今年2025年は量子物理学100年を記念した「国際量子科学技術年」ということですが、「チームわたスピ」にとっては、スピン提唱から100年の記念すべき年です。
「私にスピンをわからせて!」では、スピンの概念を理解できるようにと連載を重ねてきましたが、量子力学は直観的には分かりにくいもの。
腹を割って、本当に分かってる?と本音で話し合うべく、わたスピメンバー全員が集まりました。
和気あいあいとチームわたスピの歩みを振り返って、スピンは難しいことを再確認しましたが、分かりたいと扉を開けたことで世界は広がりました。分かることを目指して学ぶうちに、次の疑問が湧いてきます。横道にそれながらも一歩一歩進むことで、量子的に分かるひらめきの瞬間があり、知的好奇心が満たされていきました。
研究者の仕事もそれに少し似ています。研究すればするほど謎は深まり、知りたいことは終わりがありません。分かり始めるともっと分かりたくなる。深まる謎を追いかけることこそが研究の醍醐味(だいごみ)でもあるのです。
「私にスピンをわからせて!」は教科書のようにきれいにまとまってはいませんが、研究の苦しさや楽しさをのぞいてみる窓にもなっているのではないでしょうか。その裏話を、源次郎、シュレ子と一緒に聞いてみてください。

北村 源次郎:野趣あふれる美猫。上田城で母と運命の出会いを果たし、北村家の猫となったことから、真田信繁の幼名をとって源次郎と名付けられた。

「お腹をなめないように大きな襟をつけてもらってるんだニャ」

シュレ子:第4回転から登場、ヨーロッパからやってきた謎の猫。どうやらシュレディンガー家から来たらしい。好奇心の赴くまま、わたスピワールドに引き込まれて、いつのまにかレギュラーメンバーに。

母上:源次郎の母。文系だが、素粒子とスピンに興味がある。昆虫・植物が大好きで、KEK構内で撮った珍しい虫の写真を持ち歩く。プロフィールは【KEKのひと#30】「山を旅して世界を知った 北村節子さん」に詳しい。


愛媛県松山市出身。専門は、物性物理学。幼いころから磁石の不思議に魅せられて、かれこれ半世紀、今も磁石に関連した研究を続けている。

千葉県松戸市出身の理論物理学者。2020年3月まで、KEK 素粒子物理学研究所 理論センターに所属、同年4月から長崎総合科学大学 教授。
高エネルギー重イオン衝突や高エネルギーのハドロン散乱などの極限的な状況の物理に興味を持って研究している。

長年、KEKおよびフォトンファクトリーの広報を担当している研究者。専門分野は放射線生物学。

物構研の広報担当者として「わたスピ」のイラストを担当。似顔絵がよく似ていると好評。

元物構研の広報担当者。「わたスピ」の記事執筆を担当。
今回の教科書
(著者:朝永 振一郎 1974年初版発行)
『スピンはめぐる【新版】成熟期の量子力学』
2008年6月 みすず書房
今回の参考書
(著者:チームわたスピ)
『量子の世界を見る方法 「スピン」とは何か』
2022年11月 講談社ブルーバックス

あ、始まってるみたいだニャ~。

まるでオンライン同窓会ね。

なにしろ登場人物が全員KEKを卒業してるからね。小嶋さんは久しぶりにカナダからの参加ニャ。
 バンクーバーはいま何時? 夜?
バンクーバーはいま何時? 夜?  いま8時16分です。夜中ではない。
いま8時16分です。夜中ではない。 いつでしたっけ?小嶋さんと始めた第一回は。
いつでしたっけ?小嶋さんと始めた第一回は。 2018年8月です。小嶋さんがカナダに移られた頃。
2018年8月です。小嶋さんがカナダに移られた頃。  小嶋さんは、この連載のはじめの段階で、カナダに移ってしまったんですよね。私一度もリアル小嶋さんとお会いしてない。
小嶋さんは、この連載のはじめの段階で、カナダに移ってしまったんですよね。私一度もリアル小嶋さんとお会いしてない。 そうですよね。今日は久しぶりの参加です。
そうですよね。今日は久しぶりの参加です。 6年半前か。
6年半前か。 元はというと私が「分からん分からん、これどういうことなん?」と訴えたのが始まりだったんです。
元はというと私が「分からん分からん、これどういうことなん?」と訴えたのが始まりだったんです。 (笑)
(笑) でも今振り返ると、おかげで私にとっての新しいページが開かれた気がして、その世界の匂いを嗅いだだけでも幸せだった気がします。ちょっと賢くなった気がするわね。
でも今振り返ると、おかげで私にとっての新しいページが開かれた気がして、その世界の匂いを嗅いだだけでも幸せだった気がします。ちょっと賢くなった気がするわね。 (笑)
(笑) 今でも全部が分かっているとはとても思えないんだけど、漠然と「あぁ、なんかこういうことらしいな」と言うところまでは来たかなと。
今でも全部が分かっているとはとても思えないんだけど、漠然と「あぁ、なんかこういうことらしいな」と言うところまでは来たかなと。 ありがとニャー。
ありがとニャー。 そう言ってもらえると嬉しいです。
そう言ってもらえると嬉しいです。 確かにそうなんですけど、ある現象に出会ったとき、それを身の回りの現象、いわゆる古典力学的な世界になぞらえて納得するというやり方が、理解の最初のステップだと思うんですよね。
確かにそうなんですけど、ある現象に出会ったとき、それを身の回りの現象、いわゆる古典力学的な世界になぞらえて納得するというやり方が、理解の最初のステップだと思うんですよね。 なるほど。
なるほど。  単なるアナロジーのレベルで「理解した」と止まるのではなく、それとは異なる点を把握し、理解の精度を高めていくことが重要だと思うんです。
単なるアナロジーのレベルで「理解した」と止まるのではなく、それとは異なる点を把握し、理解の精度を高めていくことが重要だと思うんです。 うん。
うん。 僕、ここに来る前に記事を初めから全部読んだんですよ。
僕、ここに来る前に記事を初めから全部読んだんですよ。 ふふ。
ふふ。  あれは、深堀さんがほんとに四苦八苦した点ね。
あれは、深堀さんがほんとに四苦八苦した点ね。 僕がこのミュオンの分野に入ったそもそもの始まりが『スピンはめぐる』なんですよ。
僕がこのミュオンの分野に入ったそもそもの始まりが『スピンはめぐる』なんですよ。 おぉ(驚き)
おぉ(驚き)  でしょ?
でしょ?  いやいや、今読んだって分かんないですよ。
いやいや、今読んだって分かんないですよ。  分かんないこといっぱいあるよ。
分かんないこといっぱいあるよ。  だから大学に行っても常にスピンという単語が頭の中にあって。
だから大学に行っても常にスピンという単語が頭の中にあって。 ふーん(感心)
ふーん(感心)  その実験ではどうやって陽子のスピンを測ってたんですか?
その実験ではどうやって陽子のスピンを測ってたんですか?  そのイオン源は偏極源というか、スピンを揃えることができないので、鉄の原子核があって陽子を入れると励起状態になるんですね。非弾性散乱の過程でスピンが反転したときと、反転しなかったときで、その後に出てくるガンマ線の放出分布が変わるんです。スピンが反転すると上の方に出やすいとかそういうルールがあって、ガンマ線を測ることによってスピンが反転したかどうか分かる。
そのイオン源は偏極源というか、スピンを揃えることができないので、鉄の原子核があって陽子を入れると励起状態になるんですね。非弾性散乱の過程でスピンが反転したときと、反転しなかったときで、その後に出てくるガンマ線の放出分布が変わるんです。スピンが反転すると上の方に出やすいとかそういうルールがあって、ガンマ線を測ることによってスピンが反転したかどうか分かる。 へぇ。
へぇ。  入った陽子がそのまま出てくるんですね。エネルギーが低いと一旦中で励起状態を作って、原子核の中のどの陽子か分からなくなってから、ぽろっと非弾性散乱で出てくる。そんなことが分かって結構面白かったんですけど。
入った陽子がそのまま出てくるんですね。エネルギーが低いと一旦中で励起状態を作って、原子核の中のどの陽子か分からなくなってから、ぽろっと非弾性散乱で出てくる。そんなことが分かって結構面白かったんですけど。 覚えてるよ、今でも。小嶋さんは統計物理学の本を持ち歩いてたね。
覚えてるよ、今でも。小嶋さんは統計物理学の本を持ち歩いてたね。  つくばにミュオン源があったときですか?
つくばにミュオン源があったときですか?  そうです。つくばのミュオン源は1980年にできて2006年にシャットダウンで、僕は91年から93年くらいまでいました。
そうです。つくばのミュオン源は1980年にできて2006年にシャットダウンで、僕は91年から93年くらいまでいました。  つくばのミュオン源については、2020年に行われた「パルス中性子ミュオン発生40周年記念オンラインシンポジウム」の特設ページを見てにゃ。
つくばのミュオン源については、2020年に行われた「パルス中性子ミュオン発生40周年記念オンラインシンポジウム」の特設ページを見てにゃ。  小嶋さんは板倉さんとはどんな年関係?
小嶋さんは板倉さんとはどんな年関係? 私は多分小嶋さんの一つ下なんですよ。
私は多分小嶋さんの一つ下なんですよ。 (笑)
(笑) 3、4年生が出し物をやるんですね。恥ずかしい記憶。あっ、学園祭の出し物はスピンと関係ありません。スピンは難しすぎ。
3、4年生が出し物をやるんですね。恥ずかしい記憶。あっ、学園祭の出し物はスピンと関係ありません。スピンは難しすぎ。 私の代ではそんなスピンの実験があったというのは記憶にないですね。
私の代ではそんなスピンの実験があったというのは記憶にないですね。  板倉さんも学生の頃からスピンに興味があったんですか?
板倉さんも学生の頃からスピンに興味があったんですか?  いや特に別に。いわゆるスピンとして興味があったというわけではないです、私は。
いや特に別に。いわゆるスピンとして興味があったというわけではないです、私は。 ふーん。
ふーん。  クレブシュ―ゴルダン係数は4年生の物理数学演習に出てきて、全く分からなかった。
クレブシュ―ゴルダン係数は4年生の物理数学演習に出てきて、全く分からなかった。 なので、スピンを説明してほしいと言われたときは、実はちょっと、うーん困ったなと(笑)
なので、スピンを説明してほしいと言われたときは、実はちょっと、うーん困ったなと(笑) 僕はスピンが分かったかどうかと聞かれると、矢印書いて古典論的にどう振る舞うかというのはまぁ分かるんですね。
僕はスピンが分かったかどうかと聞かれると、矢印書いて古典論的にどう振る舞うかというのはまぁ分かるんですね。 ははは。
ははは。  ちょっと諦めに似た境地があります。
ちょっと諦めに似た境地があります。 全く同意です、分かんないんですよ。
全く同意です、分かんないんですよ。  スピンの本質は分かんないってことを言いたかったのに、これを読めばわかると言われちゃったので。
スピンの本質は分かんないってことを言いたかったのに、これを読めばわかると言われちゃったので。 それは本屋さんがつけたやつだね。
それは本屋さんがつけたやつだね。  それはある意味正しい。
それはある意味正しい。  「仮に」スピンが分かれば、量子力学が分かると。
「仮に」スピンが分かれば、量子力学が分かると。  スピン本のあとがきの初稿には「よくわからなくてもいいので安心してください」という一文があったのですが、結局消えてしまいましたね。
スピン本のあとがきの初稿には「よくわからなくてもいいので安心してください」という一文があったのですが、結局消えてしまいましたね。 例えばアマゾンのレビューを見ると「この本を読んでも結局スピンってなんだったのか分からない」というのがあるんですよ。
例えばアマゾンのレビューを見ると「この本を読んでも結局スピンってなんだったのか分からない」というのがあるんですよ。 そうなんです、それでいいんですよ。
そうなんです、それでいいんですよ。  (笑)
(笑) そういうことがすごく重要だと思う。そういうことというのはね、勉強したら分かるから、分かるために勉強するというより、勉強したらますます分からなくなるんだよということが本当は言いたいんです。
そういうことがすごく重要だと思う。そういうことというのはね、勉強したら分かるから、分かるために勉強するというより、勉強したらますます分からなくなるんだよということが本当は言いたいんです。 (笑)
(笑) そうそう。
そうそう。  簡単に分かるというのは面白くない。
簡単に分かるというのは面白くない。  そうですね。
そうですね。  どこが分からないのか分かってくるというか。
どこが分からないのか分かってくるというか。  うん、そうそう少しずつね。
うん、そうそう少しずつね。  分かるということも全部レベルが違うんですよね。
分かるということも全部レベルが違うんですよね。 そうそうそう。
そうそうそう。  それが研究というか科学なので。
それが研究というか科学なので。  そこが「分かる」というか、研究というか科学をやるということの本質、醍醐味(だいごみ)だと思うので、うまくそういうところを伝えられたらいいかなという気がしますね。
そこが「分かる」というか、研究というか科学をやるということの本質、醍醐味(だいごみ)だと思うので、うまくそういうところを伝えられたらいいかなという気がしますね。  その割にはタイトルに「わからせて」とつけちゃったから、自分で首を絞めてる。
その割にはタイトルに「わからせて」とつけちゃったから、自分で首を絞めてる。  「わからせて」であって「分かった」わけではないというね。
「わからせて」であって「分かった」わけではないというね。  「分からせて」という願望だったんだからそれでいいんじゃない。
「分からせて」という願望だったんだからそれでいいんじゃない。  わたスピは、スピンを完全に分かることを目指しているものでもなかったってことかな。
わたスピは、スピンを完全に分かることを目指しているものでもなかったってことかな。 分からないことを考え続けることが、苦しくもあり楽しくもあり。
分からないことを考え続けることが、苦しくもあり楽しくもあり。  理解というものは多層的で、もしかしたら永遠に続くものかも知れないということを見せていたのだと思います。
理解というものは多層的で、もしかしたら永遠に続くものかも知れないということを見せていたのだと思います。  分かると謎ループですね。
分かると謎ループですね。  スピンの存在を仮定しないと説明できない実験結果がいろいろある、だから「スピン」は「実在すべき自由度」だよ、というのがわたスピのメインメッセージだと思います。
スピンの存在を仮定しないと説明できない実験結果がいろいろある、だから「スピン」は「実在すべき自由度」だよ、というのがわたスピのメインメッセージだと思います。 それは難易度高い。
それは難易度高い。  こういう発散傾向も、分かる→謎のループの一種かもしれません。
こういう発散傾向も、分かる→謎のループの一種かもしれません。  あのタイトルはだれが付けたの?
あのタイトルはだれが付けたの?  あれは、付けたのは誰か覚えてませんけど、『私を野球場に連れてって』でしたっけ、あの構文ですよ。
あれは、付けたのは誰か覚えてませんけど、『私を野球場に連れてって』でしたっけ、あの構文ですよ。  そうだったね。
そうだったね。  『私をスキーに連れてって』は知ってるけど、野球場ってなんですか?
『私をスキーに連れてって』は知ってるけど、野球場ってなんですか?  あれはもともとアメリカの野球場で7回裏かなんかに必ず流れる歌なんですよね。♪タンタタタンタターンっていうメロディーの。
あれはもともとアメリカの野球場で7回裏かなんかに必ず流れる歌なんですよね。♪タンタタタンタターンっていうメロディーの。  ああ、その歌ですか。そういう歌詞がついてるんですか?
ああ、その歌ですか。そういう歌詞がついてるんですか?  そうそう、あれは向こうのデート社会学のようなもので、女の子が私を野球場に連れてってよという一つのドラマを歌った歌らしいんです。もちろん野球業界の広告でもあるんですが、それをもじって日本の映画会社が『私をスキーに連れてって』を出したんですって。
そうそう、あれは向こうのデート社会学のようなもので、女の子が私を野球場に連れてってよという一つのドラマを歌った歌らしいんです。もちろん野球業界の広告でもあるんですが、それをもじって日本の映画会社が『私をスキーに連れてって』を出したんですって。 へぇ。
へぇ。  言葉の遊びもあるんですが、当時の私としては本当に「分からせてよ!」という気持ちはありました。だってKEKに行ったら私にとってはみんなが話している言葉が火星の言葉で、その中でも頻出するのが「スピンが」「スピンが」なんだから。「スピンって何?」って聞いても「一言じゃ言えないよ」って話で終わるでしょ。
言葉の遊びもあるんですが、当時の私としては本当に「分からせてよ!」という気持ちはありました。だってKEKに行ったら私にとってはみんなが話している言葉が火星の言葉で、その中でも頻出するのが「スピンが」「スピンが」なんだから。「スピンって何?」って聞いても「一言じゃ言えないよ」って話で終わるでしょ。 ふふ。
ふふ。 中高生向けの科学本に、例えば「布を水に浸しておくとなぜ水は上がってくるの?」という話があると、「それはね、毛管現象と言ってね」という説明があるわけですよね。そこから先の「じゃ、毛管現象ってどうして起こるの?」という話はなかなかないわけ。
中高生向けの科学本に、例えば「布を水に浸しておくとなぜ水は上がってくるの?」という話があると、「それはね、毛管現象と言ってね」という説明があるわけですよね。そこから先の「じゃ、毛管現象ってどうして起こるの?」という話はなかなかないわけ。 うんうん。
うんうん。  ま、ネコと一緒に聞くなら恥ずかしくないわ、という気持ちで伺いました。
ま、ネコと一緒に聞くなら恥ずかしくないわ、という気持ちで伺いました。 これは大島さんが言い出したんですよね。
これは大島さんが言い出したんですよね。  わたスピとつけた裏話をしていいですか?
わたスピとつけた裏話をしていいですか?  もちろん。
もちろん。  その当時「ワタモテ」というアニメがあったんですよ。
その当時「ワタモテ」というアニメがあったんですよ。 ふーん。
ふーん。  そのアニメのタイトルが、『私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!』っていうんですよ。
そのアニメのタイトルが、『私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!』っていうんですよ。  (笑)
(笑) それを略して「ワタモテ」って言うので、「わたスピ」って言い出したんですけど、「私にスピンをわからせて!」じゃなくて
「私がスピンを理解できないのはどう考えてもお前らが悪い!」っていう。
それを略して「ワタモテ」って言うので、「わたスピ」って言い出したんですけど、「私にスピンをわからせて!」じゃなくて
「私がスピンを理解できないのはどう考えてもお前らが悪い!」っていう。  (一同爆笑)
(一同爆笑) ほう、いいね。それ。
ほう、いいね。それ。  略して「わたスピ」。
略して「わたスピ」。  あぁ、そうか。
あぁ、そうか。  お前らって誰?
お前らって誰?  えーっと、お前らは…。
えーっと、お前らは…。  それちゃんと書いとかないと。
それちゃんと書いとかないと。  裏の意味があったんですね。
裏の意味があったんですね。 それはないです。
それはないです。  本当に私思うんだけど、図に乗って言うんだけど…。扉を開くとこんなに面白い世界があるのに、どうして研究者の人たちはそれを分かりやすく言ってくれないの?という気持ちがあります。
本当に私思うんだけど、図に乗って言うんだけど…。扉を開くとこんなに面白い世界があるのに、どうして研究者の人たちはそれを分かりやすく言ってくれないの?という気持ちがあります。  わたスピは、掘り下げてくれたので、説明するという流れに持って行けたのがよかったかなと。
わたスピは、掘り下げてくれたので、説明するという流れに持って行けたのがよかったかなと。 電子のスピンのときはまだみんな近くにいたので、しょっちゅう村上さんの部屋に集まって長いこと、ああでもないこうでもないと言ってましたね。
電子のスピンのときはまだみんな近くにいたので、しょっちゅう村上さんの部屋に集まって長いこと、ああでもないこうでもないと言ってましたね。  物事を分かりたいなと言ったときに簡単には分からないわけなんですよね、どんなことでも。
物事を分かりたいなと言ったときに簡単には分からないわけなんですよね、どんなことでも。 (笑)
(笑) 「なんとかして分かってかましたろ」というそういう気迫に押されて僕達は説明するんだけど、説明しているうちにこっちも「なんでこれを分かってくれないんだ」と。
「なんとかして分かってかましたろ」というそういう気迫に押されて僕達は説明するんだけど、説明しているうちにこっちも「なんでこれを分かってくれないんだ」と。 お互いに「どう考えてもお前らが悪い」と思っていたということですかね。
お互いに「どう考えてもお前らが悪い」と思っていたということですかね。  (笑)
(笑) さっき大島さんが言ったタイトルがすごくいいと思ったのはそういうところで。
さっき大島さんが言ったタイトルがすごくいいと思ったのはそういうところで。 物理のセミナーとかで、何言ってるか分からないときに「それは講演者のせいだ」とみんな考えるんですよ。
物理のセミナーとかで、何言ってるか分からないときに「それは講演者のせいだ」とみんな考えるんですよ。  そうそう。
そうそう。  「お前がちゃんと説明しないから分からん」と言ってけんかになることもあるし、「こいつは説明がダメだから」といって退席してしまうこともある。
そこで対話をしてちゃんと質問に答えて、やりとりの中で理解するということが研究者にとっては日常的なことなのです。
「お前がちゃんと説明しないから分からん」と言ってけんかになることもあるし、「こいつは説明がダメだから」といって退席してしまうこともある。
そこで対話をしてちゃんと質問に答えて、やりとりの中で理解するということが研究者にとっては日常的なことなのです。  私が初めの段階で、このスピンってなんでこんなに分かりにくいのという雑談をしていたときに、たしか物構研の前の所長だったかな、スピンをちゃんと分かりやすく説明することができたら本物だと、おっしゃったんですよね。
私が初めの段階で、このスピンってなんでこんなに分かりにくいのという雑談をしていたときに、たしか物構研の前の所長だったかな、スピンをちゃんと分かりやすく説明することができたら本物だと、おっしゃったんですよね。  山田(和芳)先生ですね。
山田(和芳)先生ですね。  私はそれを聞いて意を強くして、いくら「分からん」と言ってもいいんだと思いました。多分スピンというものが、説明するには難しい概念なんだということが専門家の間でも共通認識なんだろうなと。
私はそれを聞いて意を強くして、いくら「分からん」と言ってもいいんだと思いました。多分スピンというものが、説明するには難しい概念なんだということが専門家の間でも共通認識なんだろうなと。 角運動量って何かという話から随分いろいろやりましたもんね。
角運動量って何かという話から随分いろいろやりましたもんね。  そうそうそう! あれは泣いたわ~!
そうそうそう! あれは泣いたわ~! スピンって角運動量であるってことなんですけど、それがね、なかなかね。
スピンって角運動量であるってことなんですけど、それがね、なかなかね。  北村さんが物理を取ってなかったのがよかったと思います。
北村さんが物理を取ってなかったのがよかったと思います。  そうかも知れないね。
そうかも知れないね。  ちょっと知ってる人は逆に聞けなかったりするから。「私はまっさらです」って宣言して始めたところがよかった。
ちょっと知ってる人は逆に聞けなかったりするから。「私はまっさらです」って宣言して始めたところがよかった。  「どんな恥でもかくぞ」という気持ちはあったし、実際、おばさんってなんでも聞けるのよ。
「どんな恥でもかくぞ」という気持ちはあったし、実際、おばさんってなんでも聞けるのよ。 (笑)
(笑) 宇佐美さんはいかがですか?
宇佐美さんはいかがですか?  あんまり簡単に「分かる」というのは言えないなっていうのはあるんだけど、分かると分からないの間には階段みたいに、ちょっとずつ分かっていく階段があって、上っていくとまたその先にすごい階段が続いているのが分かってくる。
あんまり簡単に「分かる」というのは言えないなっていうのはあるんだけど、分かると分からないの間には階段みたいに、ちょっとずつ分かっていく階段があって、上っていくとまたその先にすごい階段が続いているのが分かってくる。 山登りと似てないですか?
山登りと似てないですか?  そうそう、母上はよく登山する人ですから。
そうそう、母上はよく登山する人ですから。  ちょっと登ると視野が広くなって、次の山に登ろうとすると下らなきゃならなくてちょっと見えなくなるけど、みたいな。
ちょっと登ると視野が広くなって、次の山に登ろうとすると下らなきゃならなくてちょっと見えなくなるけど、みたいな。  視野が広がるとルート上だけじゃなくて、あ、ここはこういう地形だったのかということも分かるわけで、そういうことですよね。その例え、ぴったりです。
視野が広がるとルート上だけじゃなくて、あ、ここはこういう地形だったのかということも分かるわけで、そういうことですよね。その例え、ぴったりです。  階段だというの、僕もよく分かって。分からないときは全く分からないけど、分かるときってステップ状にいくんですよね。
階段だというの、僕もよく分かって。分からないときは全く分からないけど、分かるときってステップ状にいくんですよね。  うん。
うん。  量子エネルギーみたいですね。
量子エネルギーみたいですね。  あ、すごい。量子的なんですね。
あ、すごい。量子的なんですね。  パッと分かるっていうことがすごく楽しくてやってるようなものなんですよね、研究者は。
パッと分かるっていうことがすごく楽しくてやってるようなものなんですよね、研究者は。  百ゼロではないですよね。スピンだってね。全部分かると全然分かんない、それだけじゃない。
百ゼロではないですよね。スピンだってね。全部分かると全然分かんない、それだけじゃない。  完全に分からないと気が済まないという人もいて、そういう人には「スピンをわからせて!」と言ってるのに結局分かんないじゃないかと言われちゃうのかもしれないけど、なんか一つなるほどと思うものがあったらそれでいいじゃない、と思っていました。
完全に分からないと気が済まないという人もいて、そういう人には「スピンをわからせて!」と言ってるのに結局分かんないじゃないかと言われちゃうのかもしれないけど、なんか一つなるほどと思うものがあったらそれでいいじゃない、と思っていました。 大島さんはいかがでしたか?
大島さんはいかがでしたか?  私も物理学は挫折組なので…。読んでても単語レベルでしか分からないことがあって、でも知ってる単語とか知ってる現象とかに出会ったときは「あ、これ知ってる」ってテンション上がって。
私も物理学は挫折組なので…。読んでても単語レベルでしか分からないことがあって、でも知ってる単語とか知ってる現象とかに出会ったときは「あ、これ知ってる」ってテンション上がって。 (笑)
(笑) 全体の流れで興味がグーッと上がるときと、ガクッて下がっちゃって「あー分かんない」と思うときがあって。
全体の流れで興味がグーッと上がるときと、ガクッて下がっちゃって「あー分かんない」と思うときがあって。 (笑)
(笑) あそこは撃沈するよね。
あそこは撃沈するよね。  時間をかけて読んでみればまたちょっと違った階段があると思うので、また7回転8回転くらいを熟読してみようと思ってます。
時間をかけて読んでみればまたちょっと違った階段があると思うので、また7回転8回転くらいを熟読してみようと思ってます。  子供のころ、父からよく言われたの。「読書百遍、意、おのずから通ず。だぞ」と。
子供のころ、父からよく言われたの。「読書百遍、意、おのずから通ず。だぞ」と。 大島さんは去年パウリのTシャツ作ったもんね。パウリ大好き。
大島さんは去年パウリのTシャツ作ったもんね。パウリ大好き。  だけど、似顔絵で一番気に入ってるのはフント。パウリは2位です。3位がボーア。
だけど、似顔絵で一番気に入ってるのはフント。パウリは2位です。3位がボーア。 源ちゃんとシュレ子もよろしくお願いします。
源ちゃんとシュレ子もよろしくお願いします。 



関連記事:物構研トピックス「私にスピンをわからせて!」